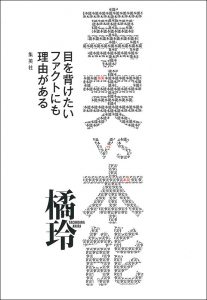安倍政権は「経済財政運営と改革の基本方針(骨太方針)」で、最低賃金を「年率3%程度を目途として、全国加重平均が1000円となることを目指す」としています。これではぜんぜん物足りないとして、「最低賃金1500円」を掲げる「リベラル派」もいます。
2018年の全国平均の最低賃金は874円で、1日8時間勤務で約7000円、1カ月フルタイム(週5日)で働いて約15万円程度です。それが1000円になれば収入は14%増(月17万円)、1500円なら70%増(月25万円)になる計算です。これなら貯蓄をする余裕もでき、「老後2000万円不足問題」も解消するのではないでしょうか。
しかし、世の中のたいていのことがそうであるように話はそう簡単ではありません。
アルバイトが8人いたとして、最低賃金が1000円になると人件費が月17万円増えるので、売上が変わらなければ1人に辞めてもらわなければなりません。最低賃金1500円なら4~5人を解雇しなければ店はやっていけません。
だったら、最低賃金を上げても従業員を解雇できないようにしたらどうでしょう。その場合は、新規採用が大幅に抑制されることになります。このとき真っ先に犠牲になるのは、学歴が低く仕事の経験のない若者たちでしょう。
フランスは最低賃金が10.03ユーロ(1220円)と先進国でもっとも高いのですが、これが若者の失業率を高止まりさせていると国際機関から指摘されています。経営者にとっては、高い賃金を払うのであれば、仕事をいちから教えなければならない若者より、即戦力になる経験者を雇った方がずっといいのです。――日本でも1990年代末からの「就職氷河期」で同じことが起き、非正規で働くしかなかった当時の若者たちが20年後にひきこもりになっていることがわかり、社会に大きな衝撃を与えました。
都道府県別で見ると、東京の最低賃金は985円でもっとも高く、東北や九州などのもっとも低い県は760円程度です。こうした地域の最低賃金を東京並みに引き上げたらどうでしょう。
全国一律の最低賃金はイタリアが行なっており、経済が好調なミラノなどの北部と、不況に苦しむナポリやシチリアなど南部の賃金は同じです。そして、これが南部の失業率を悪化させていると国際機関から指摘されています。
雇用コストが同じなら、北の企業は南に工場などを建てる理由がないし、南の労働者は他の地域に移動しようとは思いません。こうして南イタリアではひとびとが数少ない仕事を奪いあい、あぶれた若者たちはマフィアに入って非合法な仕事で糊口をしのぐしかないという、新興国のような状況になってしまいました。
隣国の韓国では、短期間に最低賃金を50%以上も引き上げた結果、失業率が上昇し雇用不安が広がっています。なかでも低所得、低学力、低熟練の「3低」の労働者(弱者)がもっとも大きな被害を受けています。
最低賃金を引き上げるとかならずマイナスの効果が生じるわけではなく、経済学者のあいだでもさまざまな議論があります。とはいえ、これが「劇薬」であることは間違いありません。
安易に「夢」をばら撒く前に、まずはこうした貴重な「社会実験」をちゃんと検討してはどうでしょうか?
参考:白川一郎『日本のニート・世界のフリーター 欧米の経験に学ぶ』 (中公新書ラクレ)
『週刊プレイボーイ』2019年7月22日発売号 禁・無断転載