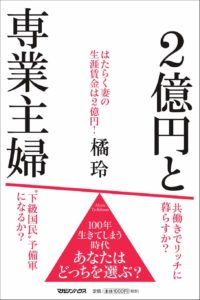新刊『2億円と専業主婦』から、出版社の許可を得てプロローグ「『専業主婦』は男の問題でもある」を掲載します。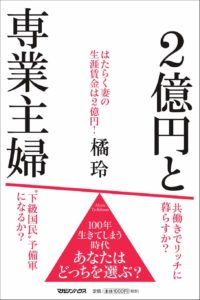
****************************************************************************************
2年前の2017年11月に本書の親本にあたる『専業主婦は2億円損をする』を出版して、はじめて「炎上」を体験しました。発売直後にYahoo! ニュースに本の紹介が掲載されると、半日で34万ページビュー、1000件のコメントがつき、そのほとんどが専業主婦と思しき方からの批判だったのです。お怒りの理由はかなり定型化されていて、ひとつは「女がそんなに稼げるわけがない」、もうひとつは「好きで専業主婦をやってるわけじゃない」です。
その当時、世間では「専業主婦は優雅な“勝ち犬”」と思われていて、「将来の夢は専業主婦」と書くJK(女子高校生)が3割もいるという調査が話題になったりもしました。そのことに驚愕したマガジンハウスの編集者の広瀬桂子さんから、「勘違いしている若い女性のための人生設計の本を書いてほしい」と依頼されたのが執筆のきっかけです。
私自身は子どもがゼロ歳のときからずっと共働き(その後は父子家庭)だったので、専業主婦にさしたる興味はなかったのですが、それでも依頼を引き受けたのは、専業主婦という選択がきわめて不合理だからです。なんといっても、大卒の女性が60歳まで働きつづけたときの平均的な生涯賃金は(退職金を除いて)2億円なのですから。
自由な市場経済において、「ゆたかになる」には経済合理的な選択を積み重ねていくしかありません。不合理な選択をしたからといってかならず貧困に陥るわけではありませんが、夫の病気や失職、離婚など、ちょっとしたきっかけで家計が行き詰まる大きなリスクを専業主婦が抱えていることはまちがいありません。ファイナンス理論の基本中の基本は、「リスクはできるかぎり分散する」です。
しかし、もはやこんなことをいちいち指摘する必要はなくなりました。親本の出版からわずか2年で、日本社会の価値観は大きく変わったからです。
それを象徴するのが、読売新聞(2017年11月5日)の読者相談コーナーに掲載された、「専業主婦 誇りを持ちたい」という投書でしょう。投稿者は40代の主婦で、「子どもが小学校高学年になり、周りのお母さんたちがこぞって仕事を始めました。専業主婦に満足していましたが、自信を持てなくなりました」と書いています。専業主婦として充実した毎日を過ごしてきたのに、「なぜ仕事をしないの。みんな頑張っているわよ」と周りのお母さんたちから何度も言われ、自分の人生に誇りが持てなくなった、というのです。
日本ではずっと「専業主婦=幸福」と考えられてきたので、ちょっと前ならこんな投書が全国紙に載ることなど考えられませんでした。でも今は、子どもの手が離れたら働くのは当たり前なのです。
とはいえ、これではまだじゅうぶんではありません。日本は「正規(正社員)」と「非正規」の格差がきわめて大きいので、出産を機に正社員を辞めて、子育てが一段落してから非正規で働いても、生涯賃金で1億4000万円もの差が出るという試算があるからです。
1億円以上も「損する」ことを考えれば、子どもが生まれてからも正社員のまま夫婦共働きを続けた方がいいに決まっています。これは米国や(北の)ヨーロッパがすでに経験してきたことで、「日本だけは特別」などということはありません。あと10年もしたら、日本でも専業主婦は「絶滅」しているでしょう。
専業主婦から共働きへの大きな変化の背景には、
- 少子高齢化で日本経済が空前の人手不足になり、女性や高齢者が働きやすくなった
- 「真正保守」の安倍政権ですら「すべての女性が輝く社会づくり」を掲げて女性の労働参加を促すようになった
- 「働き方改革」でサラリーマン(正社員)の身分が不安定になり、一部で世帯所得が減っている
ことなどが挙げられます。
これまで「保守」の政治家は、「男が外で働き、女は子育てに専念するのが日本の美しい伝統」と頑強に主張してきましたが(いうまでもなくこれは欧米先進国の習慣を採り入れたもので、江戸時代に「専業主婦」などいませんでした)、いまではだれもそんなことをいわなく(いえなく)なりました。東京都区部の公立小学校に子どもを通わせているお母さんからは、「ほとんどの母親は働いていて、クラスに専業主婦がいるとびっくりする」という話も聞きました。データでも共働き世帯が6割を超えて専業主婦世帯は少数派になっており、日本社会の近年の劇的な変化は明らかです。
こうして、専業主婦であることのアイデンティティが大きく揺らぎはじめました。
『専業主婦は2億円損をする』の紹介をネットで読んで激怒したひとたちの大半は、当然のことながら、本を読んだわけではありません。かつてなら「なにバカなこといっているの?」で笑って済ませる話でしょう。専業主婦は日本社会の「勝ち組」なのですから。
それにもかかわらず、現実に起きたのは「好きで専業主婦をやってるわけじゃない」の大合唱です。そこには、「なにが書いてあるのか、とりあえず本を読んでみて考えよう」という余裕すらありません。それほど専業主婦は追い込まれているのです。──あまりにも誤解した批判が多いため、マガジンハウスさんの英断で、『専業主婦は2億円損をする』は発売直後にもかかわらず電子版を期間限定で無料にしました。「批判はご自由ですが読んでからにしてください」と訴えた結果、任天堂のポケモンブックを抑えてアマゾンのランキングでダウンロード数1位になりました。
旧版では「(経済的に不利な)専業主婦になってはいけない」と書きましたが、もはやこのような「説教」は不要になりました。「あと10年もすれば、日本も欧米と同じように、ひとまえで「専業主婦」だと恥ずかしくていえない社会になるでしょう」と書きましたが、10年どころかたった2年でそうなってしまったのですから。
だとしたら、なぜ新書のかたちでリメイクするのか。それは、予想外の読者がいることに気づいたからです。
親本の想定読者は「高校生、大学生、結婚前の働く女性」でしたが、出産後も共働きをつづけている女性や専業主婦にも読まれました。自分の選択の正しさを確認したり、将来の選択を考えるためなのでしょう。しかしそれ以上に驚いたのは、男性の読者から大きな反響があったことです。
「結婚を考えているのですが、専業主婦願望の強い彼女に読ませます」「仕事を辞めて子育てに専念したいといっている妻を説得しようと思います」などという手紙が編集部に寄せられました。「(専業主婦の妻に読ませるために)ダイニングテーブルの上にこっそり置いた」という話も聞きました。
ここからわかるのは、「専業主婦は男の問題でもある」ということです。「2億円損をする」のは妻だけではなく、夫も同じなのですから。
いまの日本には、「自分一人の稼ぎで妻子を養い、マイホームのローンを払い、子どもを大学まで出し、老後のための資産形成をするなんてぜったいムリだ」と悩んでいるたくさんの男たちがいます。
これまで、「専業主婦の陰には、妻を専業主婦にしている夫がいる」という当たり前の事実はほとんど顧みられることがありませんでした。
働く大卒女性の平均的な生涯賃金は2億円なのですから、家計所得を増やすもっとも確実な方法が、夫が深夜まで残業したり休日に「副業」したりすることではなく、妻が働くことなのは誰でもわかります。しかし世の中には、そのことを言い出せずに悩んでいる夫がたくさんいるのです。
世帯(家計)の生涯賃金が1億円以上ちがうというのは、とてつもない「格差」です。人生の(経済的な)ゆたかさも、老後の安心感も、1億円あればまったく変わってくるでしょう。この単純な事実に、専業主婦の妻だけでなく夫もようやく気づきはじめたのです。
だとしたらいま必要とされるのは、結婚前の恋人同士で、出産を考える夫婦で、もちろん子育て中の夫婦も、一緒にこれからの人生設計を考えることができるような叩き台でしょう。その一助になればというのが、新版を世に出す理由です。
本書の第1章は親本の「1時限目 専業主婦はカッコ悪い」をすべて削除し(もはや必要ないので)、「炎上」の理由となった「女がそんなに稼げるわけがない(人的資本)」と「好きで専業主婦をやってるわけじゃない(幸福)」について、最新の資料をもとにあらたに書き下ろしました。
それを前提にして、適宜データをアップデートしながら、「どのようにしてゆたかな人生を実現するか」についての基本的な考え方といくつかのアイデアを述べていきます。金融庁の報告書に端を発した「老後2000万円不足問題」で老後と年金についての不安が再燃しましたが、しっかりとした準備(設計)があればなにも心配する必要はないことがわかるはずです。
人生を経済的な側面から考えれば、ゆたかになるためにもっとも重要なのは「家庭(世帯)の生涯賃金を最大化する」ことです。もちろんだからといって、「夫婦の時間」や「子どもへの愛情」をあきらめる必要はありません。
「母親が働くと子どもがかわいそう」とよくいわれますが、これは大きな誤解です。長大な人類の進化の歴史のなかで、「専業主婦のいる核家族」というのはわずか200年ほど前に登場した、きわめて特殊な家族制度です。それ以前の数百万年は、母親はずっと働きながら子どもを育ててきたのです。ほんとうにかわいそうなのは、貧困のなかで子どもが育つことでしょう。
自分や家族の人生を設計するときのキーワードは、「経済合理的な選択をする」です。どのような理屈をつけても、1+1=2にしかならないのですから。
さあ、これからいっしょに「幸福な人生」について考えていきましょう。