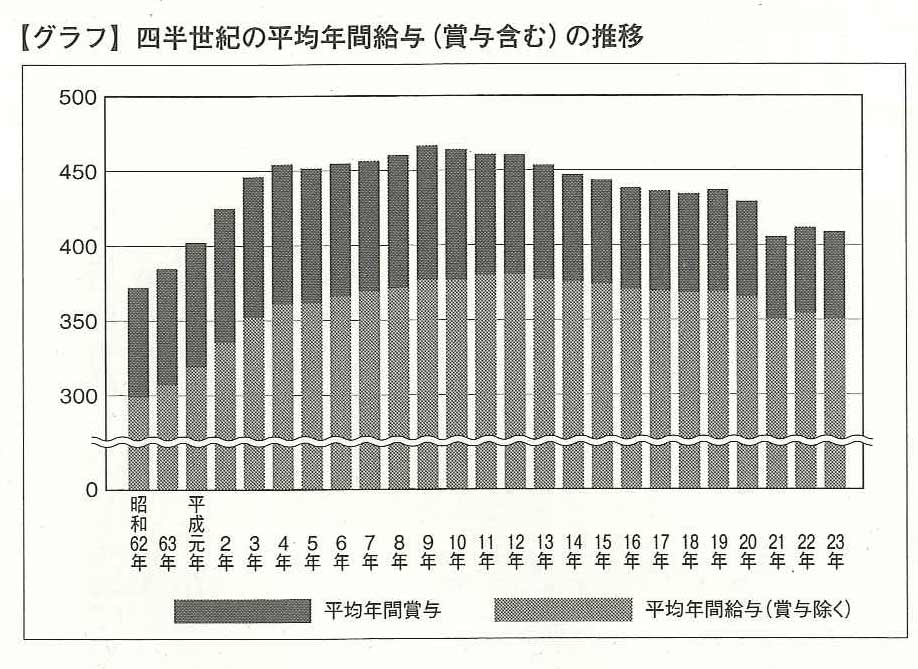母が狭心症で入院した。たいした自覚症状はなかったのだが、掛かりつけの医者に勧められて検査したところ、心臓の血管が詰まっていることがわかって、カテーテルとバルーンで拡げることになったのだ。
医師の説明では、1時間半ほどの簡単な手術で、前後を入れて3日の入院で済むはずだった。ところが実際にやってみるとカテーテルがうまく入らず、血管が破れて出血したり、血栓ができたり、けっこう大変なことになって手術が終わるまで4時間近くかかった。手術室から出てきた母はモルヒネで眠っていたが、最初のうちは部分麻酔で、血管に穴が開くところもモニタで見ていたというから、かなり怖い思いをしたらしい。
手術後は念のためにICU(集中治療室)に入ることになった。私は病院にほとんど縁がないのでICUもはじめてだが、10床のベッドは深夜や早朝に救急車で運ばれてくる患者で常にいっぱいだ。
当初はICUに1泊して一般病棟に移ることになっていたが、個室はもちろん相部屋にも空きがなく、けっきょくそこで3泊することになった。おかげで至れり尽くせりの完全看護をしてもらえたのだが、その間、病院は救急の患者を受け入れることができないのだから申し訳ないような気にもなった。
病院のスタッフと話していてわかったのは、いまやどれほどお金を持っていても個室に入るのはほぼ不可能ということだった。個室は1泊1万円から3万円まであるが、どこも順番待ちで、ほとんどの患者は相部屋で我慢するしかない。高齢の患者のなかには年金や保険でお金に不自由しないひとも多く、高い個室から埋まっていくのだ。
手術中に予想外のことが起きたからだろうが、医師は丁寧に経過を説明してくれて、看護士もみな気を使ってくれた。そんな医師や看護士が急患に声をかけながら廊下を走るのを見ると、日本の医療現場は大変だとつくづく思う。
私は日本の医療従事者の善意を疑うものではないが、しかしこうしたサービスが医療保険制度に支えられていることも間違いない。70歳以上の高齢者は医療費1割負担で、なおかつ一定額を超える高額療養費は国が支払ってくれる。だったら、できるだけ親切丁寧な医療をした方が病院も患者もハッピーだ。
アメリカでは、短時間の手術なら、その日の朝に入院して夕方には自宅に戻る。医療費の高騰で、安易な入院を保険会社が認めないからだ。
そんな「利益優先」の医療に比べれば、日本的な手厚い看護の方がずっといいと誰もが思うだろう。だがサービスの質を上げすぎたために、医療従事者の仕事が過重になっていることはないだろうか。
退院のときに、領収書をもらった。計7日間の入院で、自己負担は6万8000円。それに対して、病院に支払われる医療費の総額は200万円だった。
母を大切に扱ってくれた病院にはなんの不満もないが、このような制度がいつまで続けられるのか、正直、不安になった。
橘玲の世界は損得勘定 Vol.21:『日経ヴェリタス』2012年9月30日号掲載
禁・無断転載