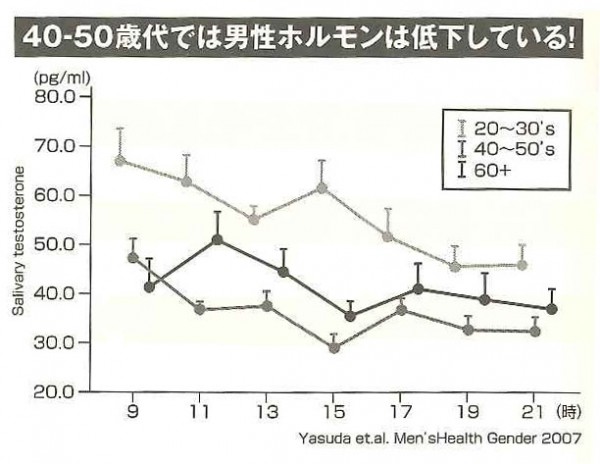日本では借地・借家人の権利が手厚く保護されている。これは戦時中、出征した兵士が帰国して住む家がなくなることを防ぐ目的で、借家契約の更新を「正当な事由」がなければ拒絶できないとしたためだ。
この正当事由は賃料不払いなどに限定されているため、賃料を払いつづけていれば、物件は実質的に借地・借家人の所有物になってしまう。賃貸住宅で暮らしているのは経済的に苦しいひとが多いから、これは弱者を保護するよい制度のように思えるが、現実には、過度の優遇が日本の不動産賃貸市場を大きく歪めてきた。
このことは、家主の立場になってみればすぐにわかる。
お金を貸せば、一定期間後に、契約に従って元本が返済される。ところが家や土地を他人に貸すと、利息のみが支払われ、いつまでたっても元本は戻ってこない。これが、資産運用にとって大きな制約であることはいうまでもない。
そのため大家は、不動産を“所有”されないようわざと賃貸物件を安普請にし、2年にいちどの更新料で退去を促し、入居の際に礼金を設定して物件の回転率を上げようとしてきた。さらには、賃料を踏み倒されないよう、契約にあたって連帯保証人を要求した。
この保証人は親族に限定されているが、高齢化で親の保証が難しくなり、連帯保証のトラブルが頻出したことで、最近では家賃賃貸保証会社の利用を条件にするところが多くなった。
賃料の半月~1カ月分(および更新時に家賃の3~5割)を支払えば保証人が不要になる制度は、一見、便利なようだが、借主からすれば負担増でしかない。信用力に問題のない優良な入居者ほど、保証会社の利用を条件とする物件を避けようとするだろう。これは、経済学でいう「逆選択」の問題だ。
大家にとっても、家賃賃貸保証がいちがいに有利とはいえない。入居費用が割高になることで、保証会社不要の賃貸住宅との競合で不利になるからだ。
従来の保証人方式は、賃料不払いの解決が大家の自己責任になるため、入居審査がきわめて厳しい。最近では、連帯保証人の印鑑証明だけでなく、収入証明まで要求するところもある。有利な物件は、本人が正社員で、保証人である親族も現役という一部のひとしか借りられないのだ。
ネットには、「契約社員や非正規社員にはぜったい貸さない」「家族に連帯保証を頼めないような人間は信用できない」などの大家の書き込みが大量にある。彼らは当然、外国人などはなから相手にしないだろう。
一時期流行った「サラリーマン大家」は、資産の大半を数戸の賃貸住宅に投資しているのだから、賃料不払いの被害は甚大だ。彼らが入居者のリスクを避けようとすることを、道徳論で非難しても仕方がない。
大家になることを夢見たのは、ごくふつうのひとたちだ。だが残念なことに、現在の借地・借家制度の下では、不動産で資産運用しようとすると差別と偏見にとらわれてしまうのだ。
橘玲の世界は損得勘定 Vol.51:『日経ヴェリタス』2015年7月5日号掲載
禁・無断転載