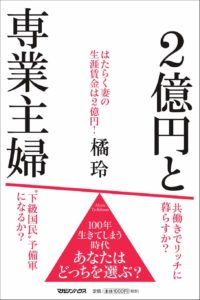黒海とカスピ海に挟まれたコーカサス山脈の南に、アゼルバイジャン、アルメニア、ジョージアの三国があります。
この地域は古来、東西の交易の要衝で、南からはペルシア、西からはギリシア・ローマ(ビザンティン)の影響を受け、独特の歴史と文化をつくってきました。アゼルバイジャンにはペルシアのゾロアスター教の遺跡が残り、アルメニアは301年、ジョージアは330年にローマ帝国に先立ってキリスト教を国教化しています。
イスラームの勢力が中近東から南コーカサス一帯まで伸張すると、16世紀にはペルシアにシーア派のサファヴィー朝が勃興します。その頃、西ではビザンティン帝国がオスマン帝国に取って代わられ、北からは「タタールのくびき」と呼ばれたモンゴルの支配を脱したロシア帝国が進出を始めました。地政学的にこの3つの帝国が衝突するコーカサスの国々は、大国の思惑に翻弄されるほかありませんでした。
アゼルバイジャンはロシア(ソ連)とペルシア(イラン)に南北に分割されたことで、本国の1000万人よりも多い1500万とも2000万ともいわれるアゼルバイジャン人がイラン北部に暮らしています。アルメニアはロシア(ソ連)とオスマン(トルコ)に東西に分割され、19世紀末のオスマン帝国末期にトルコ人ナショナリズムが高揚すると国内のアルメニア人は強制移住させられ、この混乱で100万から150万人の生命が失われました。
ソ連崩壊にともなって両国は独立しましたが、アルメニア人が多く住むアゼルバイジャン内のナゴルノ・カラバフをめぐる紛争が起き、いまは事実上独立した「未承認国家」となっています。こうした経緯でアゼルバイジャンとアルメニアは国交が断絶しており、アルメニアとトルコも隣国でありながら長く国交がありませんでした。
一方、ジョージアではソ連からの独立時にコーカサス山地や黒海沿岸の少数民族が反乱を起こし、それをロシアが支援したことで、国内に南オセチアとアブハジアという2つの「未承認国家」を抱えることになりました。かつて「グルジア」と呼ばれたこの国が国名を英語読みに変えたのは、ロシアと断絶してEUに加盟し、欧米の一員になるという決意のあらわれです。
すべての紛争がそうであるように、当事者には自分たちを「善」、相手を「悪」とする(それなりに)説得力のある理屈があります。しかし、相手側がこの善悪二元論を受け容れることはぜったいにないため、自らの正義を振りかざせばかざすほど事態は泥沼化していくのです。
これは昨今の「歴史問題」でもよく見られる光景ですが、じつは、海によって国境が明示されている日本はものすごく恵まれています。日本民族が分断されているわけでもなければ、国内に「未承認国家」があるわけでもありません。
もちろん、だからといって小さな島の帰属をめぐる隣国との争いがどうでもいいというわけではありません。しかし世界には、はるかに困難で複雑な領土問題を抱えながらなんとか平和にやっている国があることを、たまには冷静になって考えてみてもいいのではないかと、コーカサス三国を旅しながら考えました。
『週刊プレイボーイ』2019年11月25日発売号 禁・無断転載