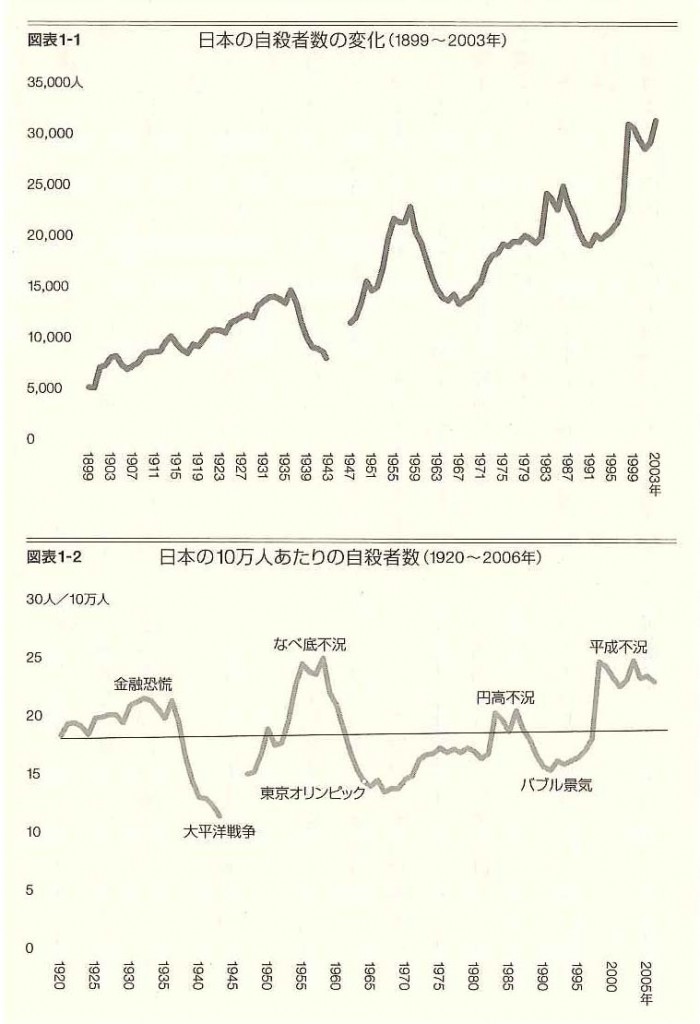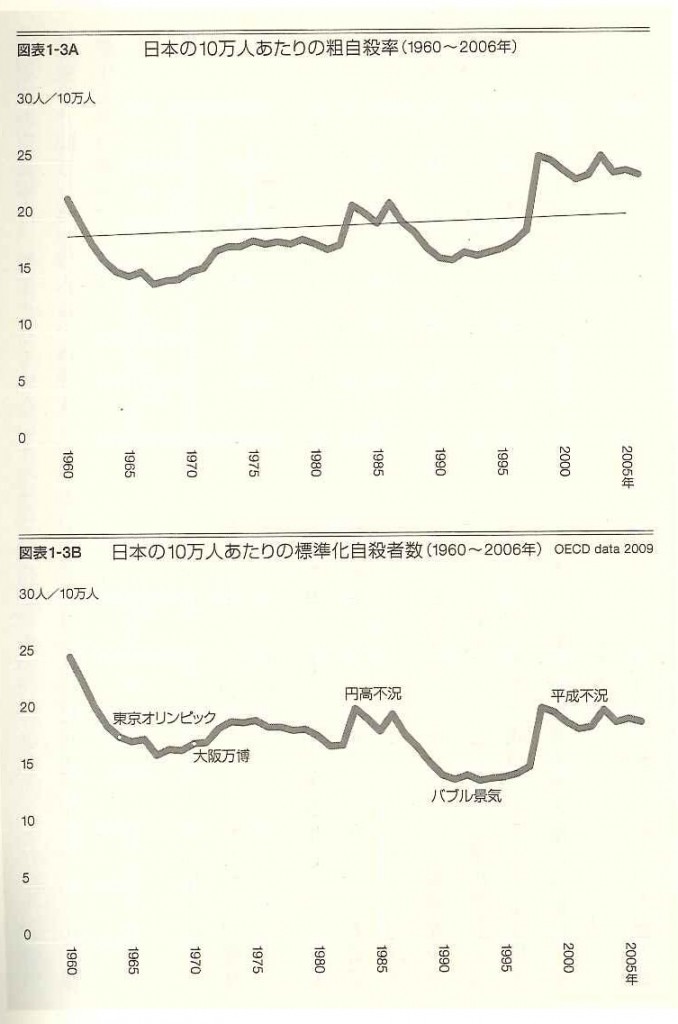2020年の夏季オリンピック開催地が東京に決まり日本じゅうが沸いていますが、ここで注目されたのがIOC委員会での最終プレゼンテーションです。とりわけパラリンピック走り幅跳びのアジア記録保持者で、東日本大震災の被災者でもある佐藤真海さんのスピーチがIOC委員のこころを大きく動かしました。
「プレゼン」という言葉がテレビのワイドショーで繰り返されたのは、おそらく前代未聞のことでしょう。なぜならこれまで、日本の社会にはプレゼンなど必要ないとされてきたからです。
サラリーマンなら誰でも知っていますが、日本の会議にはそもそも議論というものがありませんでした。根回しによってあらかじめ結論は決められており、会議とはそれを各部門の責任者が了承する儀式だからです。この根回しを組織の外に拡張したのが談合で、公共事業の入札では、各社が見積もりを出す前に落札先が決められていました。
根回しや談合でないと意思決定できないのは、日本が同質性が強く退出の難しい社会だからです。いったん恨みを買うといつまでも尾を引くのであれば、全員が納得するような解決策を探すしかありません。
日本型の組織では、上司の意を受けて現場が方針を決め、トップがそれを追認するかたちで意思決定してきました。もっとも、この手法が非効率で遅れているとは一概にいえません。旧日本軍は戦術だけあって戦略のないまま戦線を拡大し国家を破滅に導きましたが、戦後日本の製造業は現場主義のマネジメントによって世界を席巻しました。
根回しや談合は、非公式の結論を当事者の総意として誰もが受け入れる、という了解がなければ成り立ちません。組織のなかに異質なメンバー(外国人など)がいて、この前提が共有できないと日本的な意思決定は立ち往生してしまいます。
プレゼンが必要になるのは、根回しや談合が不可能な状況で決定を下さなければならない場合です。これは、組織の公正さとは関係ありません。IOCにもさまざまな黒い噂がありますが、だからこそすべてのひとを納得させるために、公開の場で優劣を競わせなければならないのです。
日本でもプレゼンが注目されるようになってきたのは、経営環境が複雑化するにつれて、根回しや談合ではすべての利害関係者を納得させることができなくなってきたからでしょう。とはいえ、こうしたやり方で最善のものが選ばれる保証はありません。
プレゼンを聞いた上でみんなで決めたのなら、決定を下した個人は責任を負う必要がありません。誰も責任を取りたくない社会では、プレゼンですら責任回避の道具に使われてしまうのです。
そう考えれば、プレゼン型の意思決定は、どうでもいい問題を扱うときに最大の効果を発揮するのかもしれません。どのプランも大したちがいがないならば、「プレゼンの上手い人間がもっとも優秀だ」と考えてもたいていはうまくいくからです。
アップルのスティーブ・ジョブスは“プレゼンの天才”と呼ばれましたが、大切な意思決定をプレゼンに頼ることはありませんでした。こころを動かすようなスピーチは外向けにとっておいて、重要な決断は常に孤独のなかで行なわれたのです。
『週刊プレイボーイ』2013年9月30日発売号
禁・無断転載