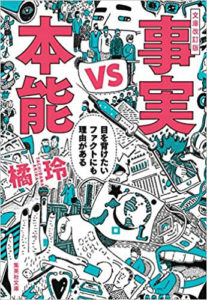出版社の許可を得て、本日発売の文庫改訂版『事実vs本能 目を背けたいファクトにも理由がある』の「まえがき」を掲載します。この表紙を見かけたら手に取ってみてください。
****************************************************************************************
2019年7月に本書の親本が刊行された後、世界は激変に見舞われました。いうまでもなく、治療法のない感染症(新型コロナウイルス)によるパンデミックという未曽有の事態です。そこでこの文庫改訂版では、構成を大幅に変え、2020年3月以降、新型コロナについて書いた文章をPart0「パンとサーカスの日本社会」としてまとめました。
本書の一貫したテーマは「事実vs本能」ですが、感染症がわたしたちの社会に引き起こした異様な現象の数々は、人間の本能が進化の過程でどのように「設計」されたのかをまざまざと見せつけました。感染予防にはなんの役にも立たないトイレットペーパーやキッチンペーパーの買い占めだけでなく、インターネットやSNSで拡散した「自粛警察」「他県ナンバー狩り」など、コロナ以前は想像もできなかった珍奇な出来事はすべて生存本能(死にたくない)で説明できるでしょう。
こうした「本能の暴走」を抑えるためにこそ「事実(エビデンス)」を示す必要があるわけですが、これでなにもかも解決できるわけではありません。
そもそも未知の感染症については専門家にもじゅうぶんな知識があるわけではなく、さまざまな仮説が提示されては書き換えられたり撤回されたりしていきます。感染症の実態を調べるPCR検査ですら、その実施範囲をめぐって専門家のあいだではげしい意見の対立があり、それがSNSなどで拡散され、党派(イデオロギー)対立と化して、あげくの果てに罵詈雑言の応酬に至りました。
専門家会議が発足して一定の指針を示したことや、欧米に比べて日本の感染者・死者数が少ないことが明らかになったことで徐々に落ち着きを取り戻しましたが、この間、なにが起きたのかが検証されるまでにはまだかなりの時間がかかるでしょう。
事実(ファクトやエビデンス)はたしかに強力な説得材料ですが、その解釈は個人の主観に任されており、党派的な対立ではそれぞれが自分にとって都合のいい事実を盾にとるようになります。
その結果、ファクトを提示すればするほど対立が深まるという皮肉な事態が起きます。新型コロナの感染状況(日本はすでに感染爆発を起こしているにちがいない)だけでなく、ウイルスの発生源(中国の武漢にあるウイルス研究所から流出した)、アジアと欧米の感染率のちがい(BCG接種で発症が抑えられる)、経済活動と感染対策(集団免疫をつけるために若年層に意図的に感染を広げればいい)などなど、専門家(にわか専門家)のさまざまな意見が現われては消えていき、現在も論争は収束する気配を見せません。
*
Part1からPart4は、2016年5月から令和元年にあたる19年6月までの3年間に「週刊プレイボーイ」に連載したコラムから、「事実vs本能」を扱ったものをピックアップしています。読み通していただければ、そこに共通する背景があることに気づいていただけるでしょう。
それはわたしたちが、「知識社会化・リベラル化・グローバル化」という巨大な潮流に翻弄されているという事実です。コロナ禍で明らかになったように、世の中を騒がすさまざまなニュースは、突き詰めれば、旧石器時代につくられたヒトの思考回路が近代以降の社会の大変化にうまく適応できないことから起きています。
そのことをより詳しく説明するために、Part5では、2011~12年にOECD(経済協力開発機構)が実施した大規模な「国際成人力調査」PIAAC(Programme for the International Assessment of Adult Competencies)について解説しています。この調査では、先進諸国の労働者のスキルについて驚くべき事実(ファクト)が明らかにされました。親本刊行後に『週刊プレイボーイ』編集部によって行なわれたインタビュー(Part6)と合わせてお読みいただければ、高度化する知識社会における「不都合な真実」が見えてくるでしょう。
世界的なベストセラーになった『FACTFULNESS(ファクトフルネス)』(上杉周作、関美和訳/日経BP社)で、ハンス・ロスリングはこう書いています。
たとえば、カーナビは正しい地図情報をもとにつくられていて当たり前だ。ナビの情報が間違っていたら、目的地にたどり着けるはずがない。同じように、間違った知識を持った政治家や政策立案者が世界の問題を解決できるはずがない。世界を逆さまにとらえている経営者に、正しい経営判断ができるはずがない。世界のことを何も知らない人たちが、世界のどの問題を心配すべきかに気づけるはずがない。
同様に、自分がどのような世界に生きているのかをまちがって理解しているひとも、自分や家族の人生について正しい判断をすることができないでしょう。
世の中には、縮尺や方位のちがう地図を手に右往左往しているひとが(ものすごく)たくさんいます。そんななかで、正しい地図を持っていることはとてつもなく有利です。
これが、たとえ完璧なものでなくても、最後は本能ではなく事実に頼らなくてはならない理由です。