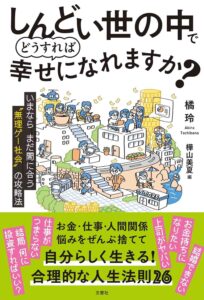ダイヤモンド社と共同で行なっていた「海外投資の歩き方」のサイトが終了し、過去記事が読めなくなったので、閲覧数の多いものや、時世に適ったものを随時、このブログで再掲載していくことにします。
今回は2021年8月26日公開の「「苦難の転換期」にアメリカ企業で出現した 《残忍なボスたち》による「いじめ」被害は日本でも繰り返されたのか?」です。(一部改変)

******************************************************************************************
コロンビア大学教授で「社会組織心理学の世界的な権威」ハーヴィー・ホーンスタインは、1995年に”Brutal Bosses(残忍なボスたち)”を出版して大きな評判を呼んだ。『問題上司 「困った上司」の解決法』(齊藤勇訳/プレジデント社)として翻訳されている四半世紀前のこの本を手に取ったのは、アメリカの会社組織のいじめやハランスメントについて語る際に必ず言及される古典だからだ。
ホーンスタインの研究が与えた衝撃を、訳者で社会心理学者でもある齋藤勇氏が「あとがき」で次のように書いている。
私はアメリカの大学に留学していたことがあり、多少なりともアメリカ社会を知っているつもりになっていただけに、本書の内容にはこん棒で殴られたような衝撃を受けた。
私が理解していたアメリカ企業の人間関係は、ビジネスライクな契約関係を基本にしたクールなもので、社員の個性を尊重する社会だと思っていた。仮に、今の上司がどうしても嫌だったら別の会社に移ればいいし、それを可能にするムービング・ソサエティー(可動性のある社会)が機能している、と思っていた。
1980年代後半から90年代前半にかけて、アメリカ企業は「苦難の転換期」を迎え、リストラ、業績評価、ポスト削減、ダウンサイジングなど、企業も労働組合も新たな出口を求めて迷走した。この苦難の時代に、「上司と部下の人間関係」をめぐって多くの問題が噴出した。
ホーンスタインは「日本語版によせて」で、「私は、日本企業に「アメリカ企業の二の舞い」を踏んでほしくない。あの転換期にアメリカ企業で出現した《問題上司》による被害を未然に防いでほしい」と書いている。わたしたちはこの言葉にこたえることができたのだろうか。
アメリカの会社員の90%以上が上司の「いじめ」を体験していた
最初に、アメリカ社会における「残忍なボス(問題上司)」との遭遇体験を紹介しよう。ホーンスタインが「職場いじめ」について調査・研究するなかで出会ったある会社員の告白だ。
上司の机は私の席の隣にあり、私はたまたま、上司の机の上に私のメガネを置いてしまいました。すると、メガネが自分の机の上に置かれるのを見た途端、上司は顔を真っ赤にして怒り出したのです。
彼は突然、私のメガネを投げつけ、メガネは飛んで壁に当たり、コナゴナに割れてしまいました。
私は、ショックのあまり小声で「何をするんですか?」としか言えませんでした。
「何もしてやしないさ。お前は、さっさと消え失せろ!」
私は、怒鳴り返そうと思いました。しかし、上司に逆らってケンカして、もし今の職場を辞めたら、私にはほかに仕事の口が見つかりそうにありません。のみならず、私は子供の学費を払わなければならないうえに、これからまた子供が生まれる、といった状況にありました。
仕方なく、私は割れたメガネと砕かれた自尊心を拾って、言われたとおりにするしかなかったのです。腹が立ち、挫折感と悔しさのあまりに涙が込み上げました。今こうして思い出すと、また悔しい思いが湧き上がってきます。
ホーンスタインの調査によれば、アメリカの会社員の実に90%以上が、サラリーマン人生の中で、一度ならず上司の「いじめ」を体験していた。また、ある1日を無作為に選んで調査すると、会社員の5人のうち1人が、何らかのかたちで上司の「いじめ」を受けていた。 続きを読む →