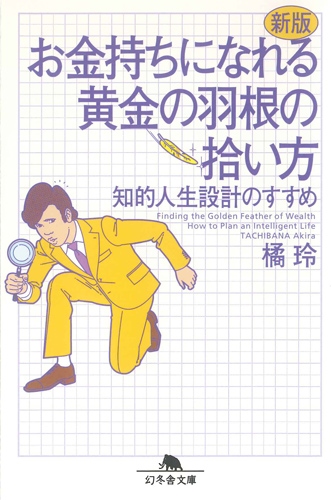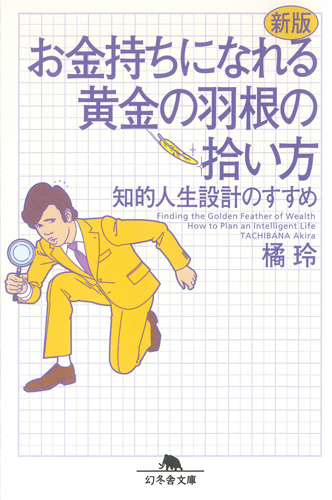『新版 お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方』の「文庫版まえがき」を、出版社の許可を得て掲載します。
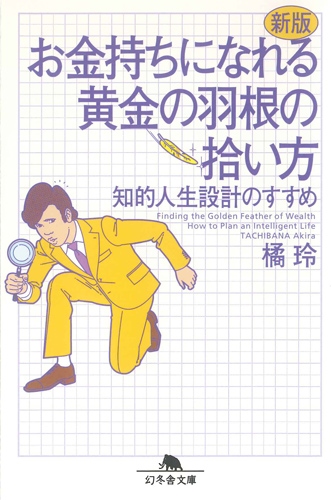
************************************************************************
本書は2014年9月に発売された『お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方2015』の文庫版です。親本は2002年12月発売の『お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方』で、改訂版を出したのは、原著の出版から10年以上が過ぎて、変わったところと変わっていないところを整理したいと考えたからです。
今回の文庫化はそれからさらに約3年が経過したわけですが、その間に重要な出来事がいくつかありました。
ひとつは2016年1月からマイナンバー(社会保障・税番号制度)の運用が始まったことです。
ふたつめは、法人に対する社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入義務が厳格化されたことです。
3つめは日本国外で保有される資産を捕捉する試みが強化され、2018年からは香港・シンガポールを含む先進国間での税務情報の自動情報交換が始まることです。
これらの政策は、日本をはじめ世界の先進諸国が置かれた環境の大きな変化を背景としています。
ICT(情報通信技術)の急速な進歩は、国家が国民をデジタル情報で管理することをますます容易にしています。
先行しているのはスウェーデンなど北欧の国々で、出生とともに個人番号が付与され、所得税の確定申告から失業保険、児童手当など社会保障の給付申請、医療費の支払い、年金情報の提供、パスポートや運転免許証の個人認証、公立図書館の利用まで、さまざまな行政サービスを自宅にいながら電子的に済ませることができます。さらには民間事業者もその情報を(本人の同意のもとに)利用でき、銀行・証券会社の口座開設、クレジットカードの利用、保険取引、賃貸住宅の契約、携帯電話の新規契約まで、「番号なしでは生活できない」といわれるほど国民生活に浸透しています。
「後進国」と見なされていたインドでも、大手IT企業インフォシスの共同創業者ナンダン・ニレカニの陣頭指揮のもと、国民一人ひとりの顔画像・指紋、目の虹彩画像を登録し、12桁のID番号を付与する生体認証システム「Aadhaar(アドハー)」の運用が2010年から開始されました。インドではカースト制度による差別と貧困が深刻な社会問題になっていますが、これによって年金や補助金の不正受給を防ぎつつ必要なひとに適切な支援を行なうことが期待されています。スウェーデンと同様、このシステムは民間にも開放されており、ムンバイなどインドの都市部では現金もクレジットカードも使わず、IDと指紋認証だけで携帯電話の契約や店舗での支払いが完結するとのことです。
こうした国々に比べれば日本はいまだに「IT後進国」ですが、国民総背番号による行政サービスの効率化や民間企業の生産性向上が目指されているのは間違いないでしょう。
日本が抱える大きな問題は、人類史上未曽有の超高齢社会を迎えたにもかかわらず、国の借金が1000兆円を超えるまで膨らんでいることです。こうした事情は、程度の差はあるものの欧米諸国も同じで、どこも歳出削減(公共事業や社会保障など行政サービスの見直し)と歳入の増加(増税)が喫緊の課題になっていますが、これだけでは有権者の支持を得ることができないので、相続税などで富裕層への課税を強化するとともに、国外に「不正に」蓄財された資産の捕捉と徴税が重要な政治課題となってきました。こうして先進国間で税務情報が交換されることになったのですが、ここでもマイナンバーが重要な役割を果たします。
すでに日本国内では、証券会社やFX(外国為替証拠金取引)会社に口座開設する際にはマイナンバーの登録が必須になりました。これは既存の口座にも広げられつつあり、いずれは銀行や保険会社の口座もマイナンバーで管理されるようになるでしょう。金融機関の口座情報がデータとして税務当局に提出され、マイナンバーによって個人資産がガラス張りになる時代がもうすぐやってきます。
こうした事情は日本の外も同じで、一部の海外金融機関は口座開設を希望する日本人にタックスID(マイナンバー)の提出を求めています。金融機関の口座とマイナンバーが紐づけられれば、国内と同様に海外の資産をガラス張りにすることも技術的には難しくありません。
税務当局からみれば、マイナンバー導入の目的は国内・国外を問わず収入と資産を捕捉し、効率的に課税できるようにすることです。しかしそれだけでは日本国の天文学的な借金を支えきれるかこころもとないので、高齢化によって雪だるま式に支出が増えていく年金や健康保険・介護保険をなんとかしなければなりません。
社会保障制度の破綻を避けるためには、年金の支給開始年齢を70歳まで引き上げるなどの抜本的な改革が不可避になるでしょうが、これは政治的にはきわめて困難なので、政治家も厚生労働省の官僚も、保険料収入の増額でなんとか糊口をしのごうとします。このようにして、厚生年金・健康保険などの保険料率(「保険税」の税率)が国会の審議もなしに一方的に引き上げられると同時に、厚生年金保険・健康保険の対象をパートなどにも拡大し、事業主である法人への社会保険加入義務が徹底されることになったのです。
2002年の親本のときから、本書では「個人」と「法人」というふたつの人格を使い分けることを提案していますが、税金とならんで大きなコストである社会保険料は人生の経済的な側面の設計に大きな影響を与えます。それとともに近年の大きな変化は、世界的な法人税の引き下げ競争が起きていることです。安倍政権は法人税の実効税率をかろうじて30%未満にしましたが、トランプ大統領は法人税率を15%に引き下げ、相続税を廃止すると明言しました(実現可能かどうかは別ですが)。日本も今後、国際競争力を維持するためにさらなる法人税の引き下げを迫られる可能性があります。
「個人」と「法人」のふたつの人格を持つ場合、税・社会保障費のコストをどちらがどのように払うかの設計が重要になります。これまでは年金・健康保険は個人で支払った方が有利でしたが、国民健康保険の財政悪化で実質保険料率が引き上げられる一方で、今後、法人税率がさらに引き下げられるならば、「個人への報酬を少なくして利益は法人で納税する」設計の方が有利になるかもしれません。
文庫版では、こうしたさまざまな環境の変化にともなう変更点を書き加えました。とはいえ、本書のコンセプトは2002年以来、なにも変わっていません。人生を経済的側面から考えるならば、それは売上と支出を管理し、利益を最大化する一種のゲームです。マイクロ法人によって「人格」を分離することは、このゲームを有利に進めるための基本戦略なのです。
幸福になるのにお金は重要ですが、お金だけでは幸福になれないこともまた真理です。人生における「経済」以外の側面については、近刊の『幸福の「資本」論』(ダイヤモンド社)で「金融資産」「人的資本」「社会資本」のポートフォリオ最適化問題として論じています。本書の続編として、手にとっていただければ幸いです。
2017年7月 橘 玲