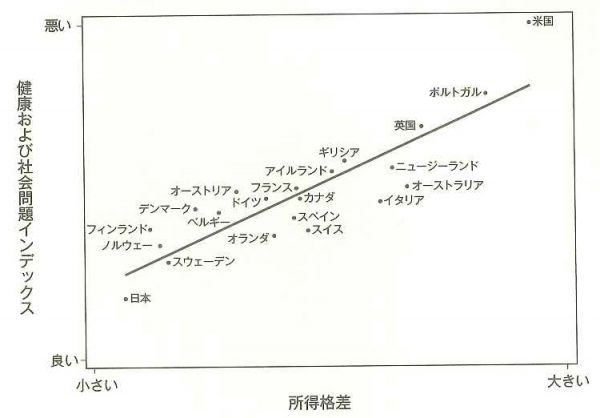総選挙が終わってから、暗い気分になる話題がつづいています。
ひとつは、不倫疑惑によって民進党を離党した女性議員の当選に対して、「無効票が1万票もあるのに834票差で当選したのはおかしい」として、「選挙をやり直せ」という電話が選挙管理委員会に大量にかかっていることです。なかには2時間半も抗議するものもあるとのことで、ここまでくると常軌を逸しています。
もちろん選管は「開票は公正に行なわれ不正はあり得ない」と述べており、抗議になんの根拠もありません。アメリカでは「ヒラリー・クリントンがかかわる小児性愛者の巣窟」とのフェイクニュースをネットに書かれたピザ店に銃をもった男が押し入り、発砲するという事件が衝撃を与えましたが、日本の民度もアメリカと変わりません。
もうひとつは、自公の与党で3分の2を獲得した選挙結果に対して、「総理の解散権の乱用」だとして、「こんな選挙は認めない」と主張するひとたちがいることです。「憲法で解散権を制限すべきだ」というのは今回の選挙が決まってから出てきた話で、それ以前にこんな改憲論は聞いたことがありません。これでは「安倍政権が勝つような選挙はするな」というのと同じで、かりに野党が政権をとるようなことがあれば自分に不利な“改憲”はすぐに忘れることでしょう。「出口調査では安倍政権を支持しないという回答が多かった」との声もありますが、これだと「選挙などせずに世論調査で政治を決めればいい」ということになってしまいます。
そのなかでもいちばんがっかりしたのは、“リベラル”な新聞が「共闘実現していたら」として、各選挙区の野党候補の得票数を単純合算し、希望の党から共産党までが共闘していれば63選挙区で勝敗が逆転したとの試算を載せていたことです。民進党が分裂したのは共産党との共闘を頑強に拒否する保守系議員がいたからで、右から左までごちゃまぜになった異様な政治組織に有権者が同じ投票をする根拠もありませんが、そんな事実をすべてなかったことにして空想(というか妄想)をわざわざ記事にするのでは“フェイクニュース”といわれても仕方ありません。
「与党圧勝」という有権者の判断を当然と思うなら、女性議員を当選させた有権者の“良識”を認めなければなりません。政治家は公職ですから「不倫」を批判されるのはしかたないとしても、選挙で当選したということは、政治家としての将来に期待する多くの有権者と強固な支援者がいたということです。これによって一定の責任を果たしたとわたしは考えますが、これに同意するなら選挙結果も有権者の判断として尊重すべきでしょう。
これは子どもでもわかるかんたんな理屈ですが、不倫疑惑の議員の当選を認めないひとと、安倍政権を「独裁」と批判して「こんな選挙は認めない」というひとはこのダブルスタンダードに気づかず、自らを“善”、相手を“悪”としてあいかわらずはげしく罵り合っています。
彼らはじつは、ものすごくよく似ています。冷静になってみれば、鏡には自分の醜い姿が映っていることに気づくのに……。
あっ、だからこのひとたちは冷静な議論を拒絶して、いつも怒っているんですね。
『週刊プレイボーイ』2017年11月6日発売号 禁・無断転載