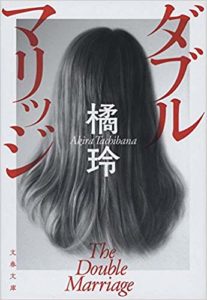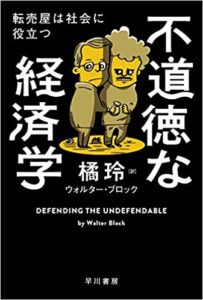昨年11月はじめに1週間ほどの日程でイランを旅しました。ドバイからのテヘラン便には女性客も多かったのですが、ヒジャブ(ベール)姿はほとんど見かけませんでした。飛行機がテヘラン空港に着くと、女性たちはカバンからスカーフを取り出して髪の毛を隠しました。
その様子を見て、最初はイランを訪れる外国人旅行者だと思いました。トルコなどイスラーム圏でも、女性がヒジャブをつけない国があるからです。ところがすぐに、私の予想が間違っていたことがわかりました。
トランプ政権のイラン敵視政策によって、アメリカとの関係はすでに悪化していました。そのためイランを訪れる外国人旅行者は減り、入国管理で外国人用カウンターに並んだのは私以外には一組だけでした。ドバイまでヒジャブなしで過ごしていた女性たちは全員、イラン人だったのです。
イランではシーラーズ、ペルセポリス、エスファハーンなどの世界遺産を回りました。どこも観光客でいっぱいで、ヨーロッパや中国からの旅行者を除けば、そのほとんどは地元のひとたちでした。経済制裁下でもイランの経済は少しずつ成長し、国内旅行できる中間層を生み出していたのです。
どの観光地でもイランの若者たちが夢中になってやっていることがありました。それがセルフィー(スマホの自撮り)です。反政府デモを警戒してイランではFacebookやTwitterなどのSNSは禁止されていますが、“インスタ映え”した自分の写真や動画をアップするサイトがあるのでしょう。
「イスラームは子だくさん」のイメージがありますが、イランでも最近は少子化が進んでいて、都市部では子どもは1人か2人がふつうになったそうです。そんな彼ら/彼女たちが青春を謳歌し“リア充アピール”しているのを見ると、宗教のちがいにかかわらず若者の価値観が急速に一体化していることがわかります。
トランプがイラン革命防衛隊の司令官を殺害したことで、戦争が始まるのではないかと世界が緊張しました。しかし私は、イランのひとたちはもはや戦争を望んでいないのではないかと感じました。
イラン革命に端を発した1980年代のイラン・イラク戦争でイランは数十万人の犠牲者を出し、地方都市には戦場で生命を失った若者たちの肖像がいまも飾られています。その当時の20代はいまでは60代で、ささやかなゆたかさを手にするとともに、海外ではヒジャブを外すくらいには世俗化しています。残酷な戦争の記憶が残るそんな親世代が、(勝てるはずのない)アメリカとの戦争に大切に育てた子どもたちを送り出すでしょうか。
アメリカとイランの緊張状態は、革命防衛隊がテヘラン上空の民間機を誤ってミサイルで撃墜するという思いがけない事態によって鎮静化しました。しかしこの不幸な事故がなくても、結果は同じだったのではないでしょうか。
現時点では、民主化を求めるイラン民衆の反政府デモに「支援」を約束したトランプの一人勝ちで、年末の大統領再選に向けて一歩前進ということになりそうです。
『週刊プレイボーイ』2020年1月20日発売号 禁・無断転載
 セルフィーする女子大生たち。鼻が白いのはプチ整形(エスファハーンのマスジェデ・ジャーメ)
セルフィーする女子大生たち。鼻が白いのはプチ整形(エスファハーンのマスジェデ・ジャーメ)