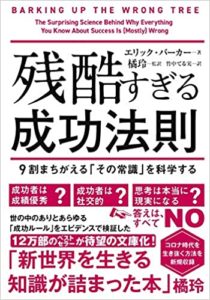新型コロナ対策の持続化給付金の民間委託に対し、疑問や批判の声が高まっています。報道を見るかぎりたしかにヒドい話で、徹底した真相究明が求められるのは当然ですが、ここではちょっと距離を置いて、なぜこんなおかしなことになるのか考えてみましょう。
話の前提として、組織のなかでいかに成功するかに「ポジティブ・ゲーム」と「ネガティブ・ゲーム」があるとします。ポジティブ・ゲームは「リスクを負ってでも一発当てて目立てばいい」で、失敗しても転職などでやり直しがきく開放系に最適な戦略です。それに対してネガティブ・ゲームは、「いっさいのリスクを負わず、目立つこともしない」で、いちど失敗すると悪評がずっとついてまわる閉鎖系での最適戦略になります。
年功序列・終身雇用の日本的雇用は、新卒でたまたま入った会社(組織)に定年まで40年以上も勤めるのですから、典型的な「閉鎖系」です。役所=官僚組織はそれに輪をかけて閉鎖的で、そこで生き残るのはネガティブ・ゲームの達人だけです。
とはいえ、どんな仕事でも失敗のリスクはついてまわります。役人の世界でも無リスクの仕事は事務・雑用などのバックオフィスだけで、これでは出世などできそうもありません。
そうなると、成功を目指す官僚にとってもっとも重要なルールは、「失敗しても責任をとらない」になります。そのときに効果的なのが「前例」で、なにか大きなトラブルが起きても、「これまでのやり方が時代に合わなくなっていた。今後は聖域なき改革に粉骨砕身したい」と、すべての責任を(引退している)前任者に負わせ、おまけに自分を“改革の旗手”に偽装することまでできてしまいます。
大きなお金が動く事業では、政治家などの利害関係者からさまざまな注文や横やりが入ります。これに対処できるのは、民間ではあり得ないような異常な状況に的確に対応できる経験とノウハウをもつ事業者だけです。有力政治家が「こんなやり方は認めん」と騒ぎだせば、すべては吹き飛んで「大失敗」になってしまうのですから。
このふたつの理由から、必然的に、官僚は大きな事業を特定の大企業につねに発注することになります。しかしいまでは公共事業は公募が原則で、これではメディアから「利権」「癒着」との批判を浴びてしまいます。
懇意の会社をダミーすればいいのでしょうが、コンプライアンスがきびしくなり、談合が刑事告発されるようになると、どこもグレーな取引を嫌がるようになりました。こうして困り果てた結果、正体不明の「協議会」をつくらざるを得なくなったのではないでしょうか。
「769億円もの事業費を(いったん)受け取るのに決算すらしていない」と批判されましたが、これは怠慢ではなく意図的なものでしょう。「幽霊協議会」の名ばかり役員でも、決算印を捺してしまえば「責任」をとらなくてはならないのですから。
このようにすべてのプレイヤーが「責任をとらない」というネガティブ・ゲームをしていると考えれば、不可解な出来事でも話のつじつまが合ってきます。これが日本社会の本質ですから、大なり小なり、すべてのひとが似たような体験をしていることでしょう。
『週刊プレイボーイ』2020年6月22日発売号 禁・無断転載