作家・橘玲(たちばなあきら)の公式サイトです。はじめての方は、最初にこちらの「ご挨拶」をご覧ください。また、自己紹介を兼ねた「橘玲 6つのQ&A」はこちらをご覧ください。
黒人保守派が アファーマティブ・アクションを否定する理由
ダイヤモンド社と共同で行なっていた「海外投資の歩き方」のサイトが終了し、過去記事が読めなくなったので、閲覧数の多いものや、時世に適ったものを随時、このブログで再掲載していくことにします。
今回は2018年9月13日公開の「黒人保守派のソーウェルが アファーマティブ・アクションを否定する理由」です。(一部改変)

******************************************************************************************
2018年8月30日、アメリカ司法省はハーバード大学の入学選考でアジア系の学生が不当に排除されているとの意見書を提出した。
ハーバード大が2013年に行なった学内調査では、学業成績だけならアジア系の割合は全入学者の43%になるが、他の評価を加えたことで19%まで下がった。また2009年の調査では、アジア系の学生がハーバードのような名門校に合格するには、2400点満点のSAT (大学進学適性試験)で白人より140点、ヒスパニックより270点、黒人より450点高い点数を取る必要があるとされる。
米司法省の意見書は、「公平な入学選考を求める学生たち(SFA)」というNPO団体が、ハーバード大を相手取って2014年にボストンの連邦地裁に起こした訴訟のために提出されたもので、同団体は白人保守派の活動家が代表を務めている。トランプ大統領に任命された共和党保守派のジェフ・セッションズ司法長官も、「誰も、人種を理由に入学を拒否されるべきではない」と述べた。こうした背景から、今回の意見書は、白人に対する「逆差別」として保守派が嫌悪するアファーマティブ・アクション(積極的差別是正措置)撤廃に向けての布石ともいわれている(「「ハーバード大、アジア系を排除」米司法省が意見書 少数優遇措置に波及も」朝日新聞2018年9月1日)。
「アンクル・トム(白人に媚びを売る黒人)」と呼ばれて
奴隷解放宣言100周年の1963年、マーティン・ルーサー・キングは「私には夢がある(I Have a Dream)」の有名な演説のなかで、「肌の色でなく人格の中身によって」認められる社会を目指そうと訴えた。これが「カラー・ブラインド主義」で、当たり前のことだと思うかもしれないが、その後、アメリカ社会に大きな混乱をもたらすことになる。なぜならアファーマティブ・アクションでは、公的機関の雇用や公共事業の入札、大学への入学枠などで、「肌の色」による優遇(差別是正)が行なわれているからだ。
これに対して「逆差別」される側の白人やアジア系から不満が出るのは当然だが、じつは黒人のなかにも「アファーマティブ・アクションを廃止すべきだ」と主張する一派がいる。彼らは「黒人保守派」と呼ばれ、アメリカ政治のなかでは特異な地位を占めているが、その根拠はキングの「私には夢がある」の一節だ。「肌の色でなく人格の中身によって」国民を平等に評価するのなら、大学への入学も人種に関係なく(カラー・ブラインドで)得点のみで決めるべきだ、となるほかない。
黒人保守派としては、日本ではシェルビー・スティールの『黒い憂鬱 90年代アメリカの新しい人種関係』(李隆訳/五月書房)などがよく知られている。
スティールは1946年に、シカゴでトラック運転手をしていた黒人の父親と、ソーシャルワーカーだった白人の母親のあいだに生まれた。大学で政治科学や社会学を学んだあと、ユタ大学で英語学の博士号を取得し、サンノゼ州立大学で英文学を教えたのち、フーバー研究所のフェローとなった。双子の兄弟のクラウド・スティールも学者で、スタンフォード大学教育学部長などを務めた。
こうした経歴からもわかるように、「肌の色を気にせずにすむ社会」を目指す黒人保守派は典型的なエリートで、白人保守派から支持される一方、黒人活動家やリベラル派の白人からは「アンクル・トム(白人に媚びを売る黒人)」の蔑称で毛嫌いされている。
経済学者のトーマス・ソーウェルはスティールと並ぶ黒人保守派の代表的な論客だが、日本ではほとんど知られていない。唯一『入門経済学 グラフ・数式のない教科書』 (加藤寛監訳、堀越修訳/ダイヤモンド社)が翻訳されているが、これは「専門用語を使わず、さらに関数もグラフも登場しないため、経済学に必須の数学が苦手な人でも十分理解できる」経済学の入門書で、手に取ったひとはソーウェルの政治的立場はもちろん、黒人であることもまったく気づかないだろう。
黒人保守派はなぜ、公民権運動で勝ち取った黒人の権利を放棄するような主張をするのだろうか。それを知りたくて、ソーウェルの自伝“A Personal Odyssey(私の人生航路)”を読んでみた。以前紹介した“The Idealist”と同様にとても面白い本だが、本書も同様に翻訳されることはなさそうなので、この機会に紹介してみたい。
マイナ騒動は「老人ファシズム」である 「紙の保険証残せ」はエセ正義
『週刊文春』(2023年8月17・24日夏の特大号)に寄稿した記事ですが、ネットで読めなくなっているようなので、出版社の許可を得て『DD(どっちもどっち)論 「解決できない問題」には理由がある』(集英社)から転載します。
関連記事:自ら道徳的責任を引き受けた藤島ジュリー景子こそまっとうだ
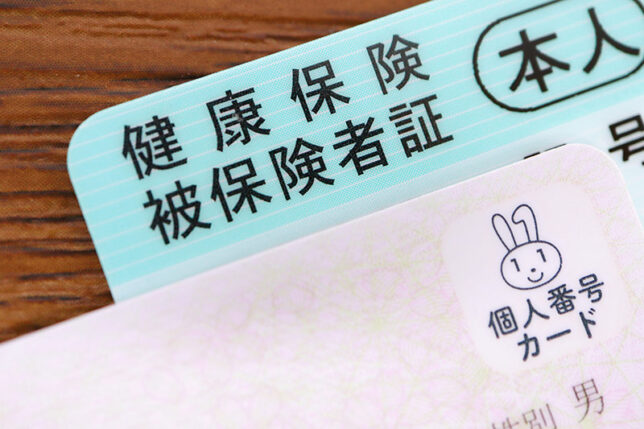
******************************************************************************************
「できない」ことは権利なのか?
「なんなんだ、この店は。客をバカにしているのか!」
ランチを食べに近所の店に入ろうとしたら、いきなり怒鳴り声がして、顔を真っ赤にした高齢の男性がぶつかってきた。妻なのだろう、同じくらいの年の女性が顔を伏せて、あとに続いた。
その店では、注文はテーブルに置かれた専用のタブレットで行なうことになっている。昼時でレジ前には精算の列ができており、スタッフはみな配膳に追われていた。その男性は席に案内されたもののタブレットの使い方がわからず、放置され、ないがしろにされたように感じたらしい。
人口が減り続ける日本ではどこも人手が足りず、タッチパネルやORコードを使ったオーダーも当たり前になった。店内を見渡すと、みんなごくふつうにタブレットで注文している。
だとしたら、「できない」ということは権利なのか?
2024年秋に紙の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードと一体化するとの方針が高齢者の不安を引き起こし、支持率低下に焦った岸田首相は、マイナ保険証を持たないひとに一律に交付する「資格確認書」の有効期限を5年に延長すると発表した。混乱の原因には政府の対応の稚拙さがあるものの、この間の「マイナ問題」の報道はあまりに偏向しているのではないか。
メディアが大きく取り上げた事例に、公金受取口座の誤登録がある。マイナカード普及を目的とした最大2万円分のポイント付与キャンペーンでは、口座情報の登録が条件とされた。そこで自治体が登録を代行する支援窓口を設けたところ、そこに市民が押し寄せて現場が混乱し、別人の口座を誤って登録したケースが900件あまり判明したという。
これはずいぶん批判されたが、メディアは本質的な「問題」に触れていない。それは、マイナンバーと銀行口座との紐づけは、本来、マイナポータルでユーザー自身が行なうようになっていることだ。
だとしたら自治体は、「できない」高齢者の面倒を見るのではなく、マイナポータルの使い方を説明した冊子を配るだけでよかったのではないか。ほとんどの国民は、自分で手続きしているのだから。
政府が推進する行政のデジタル化の目的は、市民が窓口に行かなくても行政サービスを受けられるようにすることだ。そのための基幹インフラがマイナンバーであるにもかかわらず、マイナポイントのために窓口に高齢者が殺到したのは皮肉というほかない。 続きを読む →
ポピュリズム政党の躍進の背後にある不都合な事実(週刊プレイボーイ連載652)
7月20日に行なわれた参院選では、結党5年目の参政党が大きく票を伸ばし、主要政党の一角を占めたことが衝撃を与えました。
コロナ禍の2022年に行なわれた参院選では「反ワクチン」を掲げ、ノーマスクで選挙戦を行なうなど一部で注目されましたが、当選したのは比例区の代表1人で、「陰謀論の泡沫政党」と見なされていました。ところがその後、地方選挙で着実に議席を獲得するなどして地盤を築き、24年の衆院選で3議席を獲得、今回の参院選の大躍進へとつなげたのです。
参政党の特徴は、YouTubeなどSNSで注目を集める一方で、その過激な主張から新聞やテレビなどのマスメディアから事実上排除されてきたことです。欧米のアウトサイダー政党では、カリスマ的なリーダーがSNSのインフルエンサーとなって移民排斥などの極右的な主張をし、支持者は「リベラルなエリート」が社会を支配しているという陰謀論(ディープステイト)を信じています。既成の政治やマスメディアへの不信感が強いなど、参政党支持者もこうした傾向を共有しているとされます。
日本では出口調査で性別や年代くらいしか尋ねませんが、海外では学歴や年収、職業まで質問しており、アウトサイダー政党の支持者が平均的には高卒・高校中退などの低学歴で、非正規などの不安定な仕事をしていて、年収も低いという結果が出ています。ここから、「グローバル化から取り残されたひとたち」が極右政党を支持している、というのが定番の説明になっています(ただし異論もあります)。
参政党の街頭演説に集まった支持者へのインタビューでは、メディアに批判的というより、そもそも新聞の政治報道やテレビの政治番組にほとんど興味がないらしいことがうかがえます。だとしたら、メディアのファクトチェックになんの効果もないのは不思議ではありません。
それに加えて、「ファクト(エビデンス)をベースに論理的になにが正しいか議論すべきだ」というルールそのものが拒否されているのかもしれません。ファクトがどうであれ、「批判されているのは真実をいっているからだ」というわけです。
参政党代表の神谷宗幣氏が過去の発言を批判され修正しても、支持者がまったく気にしないのも同じです。そればかりか、「言葉尻をとらえて揚げ足を取っている」「悪意で誤解して批判の材料にしている」と、ますます支持を強固にしている可能性もあります。
文科省は今年7月、小学校6年生と中学3年生を対象に行なった全国学力テストで、国語の記述式問題の正答率は25.6%、文章を読んで自分の考えと理由を書く問題では無解答率が3割に上ったと発表しました。
こうした結果は「教育が悪い」で済まされますが、成人を対象として仕事に必要な能力を国際比較するPIAAC(ピアック)でも、日本人の3人に1人が基本的な国語能力に欠けることが示されています。
メディアや識者は認知能力の分布の多様性という「不都合な事実」から目を背けていますが、これでは日本や世界で起きていることが説明できず、ますます不信が高まるばかりではないでしょうか。
『週刊プレイボーイ』2025年8月4日発売号 禁・無断転載

