『週刊文春』(2023年8月17・24日夏の特大号)に寄稿した記事ですが、ネットで読めなくなっているようなので、出版社の許可を得て『DD(どっちもどっち)論 「解決できない問題」には理由がある』(集英社)から転載します。
関連記事:自ら道徳的責任を引き受けた藤島ジュリー景子こそまっとうだ
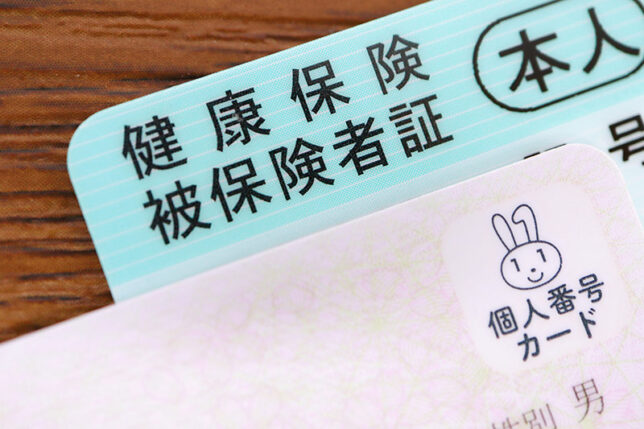
******************************************************************************************
「できない」ことは権利なのか?
「なんなんだ、この店は。客をバカにしているのか!」
ランチを食べに近所の店に入ろうとしたら、いきなり怒鳴り声がして、顔を真っ赤にした高齢の男性がぶつかってきた。妻なのだろう、同じくらいの年の女性が顔を伏せて、あとに続いた。
その店では、注文はテーブルに置かれた専用のタブレットで行なうことになっている。昼時でレジ前には精算の列ができており、スタッフはみな配膳に追われていた。その男性は席に案内されたもののタブレットの使い方がわからず、放置され、ないがしろにされたように感じたらしい。
人口が減り続ける日本ではどこも人手が足りず、タッチパネルやORコードを使ったオーダーも当たり前になった。店内を見渡すと、みんなごくふつうにタブレットで注文している。
だとしたら、「できない」ということは権利なのか?
2024年秋に紙の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードと一体化するとの方針が高齢者の不安を引き起こし、支持率低下に焦った岸田首相は、マイナ保険証を持たないひとに一律に交付する「資格確認書」の有効期限を5年に延長すると発表した。混乱の原因には政府の対応の稚拙さがあるものの、この間の「マイナ問題」の報道はあまりに偏向しているのではないか。
メディアが大きく取り上げた事例に、公金受取口座の誤登録がある。マイナカード普及を目的とした最大2万円分のポイント付与キャンペーンでは、口座情報の登録が条件とされた。そこで自治体が登録を代行する支援窓口を設けたところ、そこに市民が押し寄せて現場が混乱し、別人の口座を誤って登録したケースが900件あまり判明したという。
これはずいぶん批判されたが、メディアは本質的な「問題」に触れていない。それは、マイナンバーと銀行口座との紐づけは、本来、マイナポータルでユーザー自身が行なうようになっていることだ。
だとしたら自治体は、「できない」高齢者の面倒を見るのではなく、マイナポータルの使い方を説明した冊子を配るだけでよかったのではないか。ほとんどの国民は、自分で手続きしているのだから。
政府が推進する行政のデジタル化の目的は、市民が窓口に行かなくても行政サービスを受けられるようにすることだ。そのための基幹インフラがマイナンバーであるにもかかわらず、マイナポイントのために窓口に高齢者が殺到したのは皮肉というほかない。
日本の最大の課題は高齢者が多すぎること
デジタル化は市民の利便性向上だけでなく、政府のコストを減らすことも目的としている。社会が多様化するにつれてひとびとが行政に求めるサービスは増えていくが、人材・予算などの資源は有限だ。非効率なやり方を続けていれば、いずれ行き詰ってしまう。
人類史上未曾有の超高齢社会を迎えた日本の最大の課題は、高齢者が多すぎることだ。政府の人口推計では、2040年には年金受給年齢である65歳以上が全人口の35%と3人に1人を超える。それにともなって年金、医療、介護などを合わせた社会保障給付の総額は190兆円に達すると見込まれている。
20年後の人口を1億人、現役世代を5000万人とすれば、単純計算で現役世代1人あたりの負担は年400万円弱になる。このような社会が持続可能かは、すこし考えれば誰だってわかるだろう。
23年度の国家予算約114兆円のうち、(税から支出される)社会保障費が32.3%、国債の利払い・償還にあてられる国債費が22%で、合わせて5割を超えている。しかもこれらの経費は、高齢化や国債発行増にともない毎年確実に増えていく。それに対して「大幅増額」の防衛費は、予算全体の6%弱だ。ロシアのウクライナ侵攻以降、「中国の脅威」が声高に唱えられているが、日本社会にとっての最大の脅威は人口減と高齢化の圧力なのだ。
1950年には65歳以上1人に対して15〜64歳人口が12.1人だったが、いまから約40年後の2065年にはそれが1.3人になると見込まれている。1人の現役世代が、子育てと親の介護をしながら、さらに高齢者1人を支えなければならない。
いまの若者はこのことをよく知っており、将来の経済的な不安が少子化の最大の原因になっている。これでは、「異次元の少子化対策」をしたところでなんの効果もないだろう(ただし子育て支援は必要だ)。
このような日本の現状を考えれば、徹底したデジタル化によって行政コストを削減する以外に道はない。それにもかかわらずメディアは、まるで「正義」であるかのように、「紙の保険証を残せ」と大合唱している。
毎年600万件起きているトラブルを無視
保険証をデジタル化するのは、医療の質を維持しつつ、今後、急速に膨らむ医療費を抑制するためだ。この改革を実現するには、患者が自分の医療情報を管理するだけでなく、医療機関のあいだで電子カルテや投薬情報を共有できる仕組みが不可欠になる。
ここまでの「総論」は誰もが同意するだろうが、問題は、患者が紙の保険証を使っていれば病院はデジタル化する理由がなく、病院がデジタル対応していなければ、患者は紙の保険証のままでいいと考えることだ。
メディアは「マイナ保険証に切り替えた利用者の半数以上がメリットを感じていない」とさかんに報じているが、これはマイナ保険証の問題ではなく、デジタル化を拒んでいる医療機関の問題だ(同様に、マイナカードを使った証明書の誤交付は、システムを開発した富士通の問題だろう)。
医療のデジタル化が機能するには一定数以上の利用者が必要になる。紙の保険証を廃止しなければならない理由は、そうしないといつまでも医療機関が対応しようとしないからだ。「デジタルと紙の保険証を併用し、徐々に切り替えていけばいい」との主張もあるが、この「切り替え」にいったい何年(あるいは何十年)かかるのか。
アナログの情報をデジタルにするには、どうしても手作業が必要になる。そのため自治体や健保組合に過度の負担が生じ、それがミスを生んでいる。政府は「総点検」を指示しているが、これではさらに現場を疲弊させるだけだろう。
だとしたら、最初にこうした事情を国民に説明し、「一定数の誤登録は仕方ないが、それで不利益が生じることはない」と約束すべきだった。膨大な手作業を、わずかなミスもなく完璧にこなさなくてはならないというのが非現実的なのだ。
メディアも(おそらくは)このことを知っていながら、登録担当者の失策をこの世の終わりであるかのように大々的に報じている。他者にこれほどの完璧を求めながら、新聞紙面にしばしば「お詫びと訂正」が載るのはどういうわけなのか。
健保組合などでの入力ミスで、マイナ保険証に別人の情報が登録されたケースは7000件あまりとされる。それに対して厚労省の担当者は国会で、紙の保険証による手続きミス(医療機関への返戻)が年間600万件発生しており、オンラインの資格認証システムの導入によって、これが劇的に減ってきていると答弁した。
7000件の誤登録(マイナ保険証の利用登録6500万件の0.01%)を一面で大きく報じる新聞は、毎年600万件起きているトラブルをなぜ無視しているのか。
アナログとデジタルの基本すら理解できない
マイナカードが運転免許証や保険証と一体化できるのは、公的な本人認証機能があるからだ。仕組みは銀行のキャッシュカードと同じで、ICチップとパスワードによって、カードの真正な所有者だと確認できた場合に「本人」と認証する。
ところがアナログとデジタルの基本すら理解できないメディアは、紙の保険証でもマイナ保険証と同じ行政サービスが受けられるとして、デジタル化に反対している。これがどれほど馬鹿げているかは、通帳とキャッシュカードで考えるとわかりやすい。
通帳を窓口にもっていっても、ATMマシンを利用しても、銀行のデータベースにアクセスして口座からお金を引き出すことができる。だがこれによって、「紙の通帳はキャッシュカードと同じだ」とか、「通帳の方が安心だからATMを廃止しろ」などと主張する者はいないだろう。
アナログな通帳や保険証をデジタルのデータベースにつなぐためには、必ず手作業が必要になり、そこでコストが発生する。逆にいえば、コストを度外視すれば、デジタルと同じことをアナログで実現することは理屈の上では可能だ。
ATMを廃止しても、全国のコンビニに銀行窓口を設置すれば、いまと同じ利便性を維持することはできるだろう。だがそのためには、天文学的なコストが必要になる。「マイナ保険証と紙の保険証は同じ」という主張は、デジタル化が遅れることで生じるコストは若者や現役世代に押しつければいいといっているのと同じだ。
マイナ保険証への一体化に反対する理由として、認知症の高齢者が入居する施設が保険証管理で困惑していることをメディアは大きく取り上げた。現在は紙の保険証を預かっているが、職員がマイナカードだけでなく暗証番号も管理するのは負担が大きすぎるという。
これも一見、「弱者」の立場からの正当な批判に思える(だから政府も対応に苦慮した)。だがよく考えると、メディアがいうように紙の保険証を残したとしても、この問題はまったく解決できない。なぜなら、これから認知症の高齢者の数はますます増えていくから。
認知症の発症率は65歳以上の約16%、80代後半だと男性の35%、女性の44%で、2020年に600万人だった認知症患者は、25年には675万人に増えると予測されている。画期的な治療法が発見されないかぎり、20年後には800万〜1000万人に達するだろう(その後厚労省が、2040年には認知症者と前段階の軽度認知障害を加えると、65歳以上の1200万人、およそ3人に1がなんらかの認知的な障害を抱えるとの推計を発表した)。
当然のことながら、これだけの患者を介護するには施設がまったく足りない。問題は保険証の管理ではなく、「管理」できない認知症者が街に溢れることだ。
ところがメディアはこの「不都合な事実」を無視し、政権批判に都合のいいエピソードとして、高齢者施設の入居者を利用している。問うべき「問題」は、施設に入居できない認知症者をどのように医療・介護サービスにつなぐかのはずだ。
現代のラッダイト運動
キャッシュカードとパスワードが盗まれるとATMから現金を引き出されるのと同じように、マイナカードとパスワードが第三者の手に渡ると簡単に「なりすまし」ができる。これがパスワードを使ったデジタル認証のリスクだが、だからといって紙に戻すことはなんの解決にもならない。保険証には顔写真すらないのだから、デジタル以上に詐欺の温床になるに決まっている。
原理的に考えるならば、本人認証とは、アナログな身体をデジタルのデータベースにどのように紐づけるかという問題だ。そしていまのところ、パスワードに代わる方法はひとつしかない。それが生体認証だ。
スマホは指紋認証と顔認証を取り入れたことで、セキュリティが大きく高まった。多くの金融機関はこれを利用して、指紋認証だけで送金を完結できるようにしている。それ以外の生体認証には眼の虹彩や手首の静脈などがあり、究極の生体情報はDNAだ。
マイナ保険証は2022年1月から顔認証に対応するようになったが、5年に1回、顔写真を撮影しなければならないという制約がある。それに対して虹彩で公的な本人認証ができれば、カードもパスワードも不要になるから、それをどのように管理するかで悩む必要もない。それに加えて、(これからどんどん増えていくであろう)施設に入居できない認知症者にも、虹彩をスキャンすることで医療・介護、生活保護などの行政サービスを効率的に提供できるだろう。
これは机上の空論ではなく、インドが導入した先進的な個人ID制度「アーダール」は指紋と虹彩を登録し、コロナ禍では10億回のワクチン接種をスマホのアプリだけで混乱なく終わらせた(それに対して日本では紙の接種券を郵送した)。だとしたら、高齢者施設で生体認証を先行して始めればいいではないか。
19世紀前半、産業革命で織物工業に機械が導入されたことで、イギリスの労働者たちが大規模な機械破壊運動を始めた。技術の進歩に適応できない者たちは「ラッダイト」と呼ばれた。
リベラリズムとはもともと、科学や技術によってよりよい社会をつくっていこうという進歩主義を含意していたはずだ。ところが「リベラル」を自称するメディアは、前向きな提案をいっさいせず、紙とFAXの世界に戻せという「現代のラッダイト運動」を主導している。
コロナ感染拡大前の2020年1月、自民党の政治家(山田太郎参議院議員)がSNSで「あなたのために政治に何ができますか?」と訊いたところ、20代、30代の若者たちから「苦しまずに自殺する権利を法制化してほしい」との要望が殺到した。これはディストピア小説ではなく、現在の日本の話だ。
5日間の実施期間に2200件あまりのコメントが集まったが、90歳の祖母を60歳の母親と介護する30歳の独身女性は、未来には絶望しかなく、「60歳くらいで両親共々命をたちたい」と書いている。
「リベラル」を自称するメディアや識者は、「高齢者に押しつぶされる」という若者の不安を、「世代間の対立を煽るな」といって抑えつけてきた。その結果、高齢者を少しでも「不安」にすることはいっさい許されない、「老人ファシズム」ともいうべきグロテスクな社会が生まれた。
紙の保険証を残せば高齢者は「安心」かもしれないが、デジタル化が遅れるほど行政コストは膨らんでいく。このままでは、親を介護し看取ってから、自分は安楽死(自殺)したいと思っているやさしい若者たちの声は誰にも届かない。
岸田首相や河野デジタル相は、デジタル社会を実現しなければならない理由を率直に国民に語り、「高齢者切り捨て」というメディアの批判に対しては、「若者を切り捨てるな」と堂々と反論すべきだ。
『週刊文春』(2023年8月17・24日夏の特大号)に寄稿した「『紙の保険証残せ』はエセ正義 マイナ騒動は『老人ファシズム』である」をを『DD(どっちもどっち)論 「解決できない問題」には理由がある』に収録、それを一部加筆修正した。
禁・無断転載
