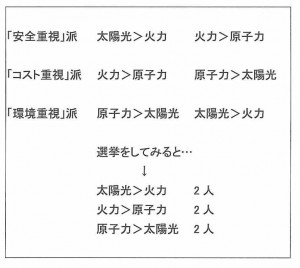『大震災の後で人生について語るということ』を執筆するきっかけとなった大震災の夜のことを、過去のエントリーと一部重複しますが、掲載します。
* * * * * * * *
ジグムント・フロイトに学んだウィーンの高名な精神医学者ヴィクトール・エミール・フランクル博士は、ナチス・ドイツがオーストリアを併合すると、ユダヤ系の出自を理由に家族とともにアウシュヴィッツに送られ、両親と妻、2人の子どもをガス室で失いました。強制収容所から奇跡的に生還した後、フランクル博士は、極限状況のなかで生き延びるために苦闘するひとたちの心理を冷静に分析した『夜と霧』を発表します。
世界的なベストセラーとなったこの本の冒頭で、博士はカポーと呼ばれる囚人たちについて書いています。カポーは囚人のなかから選抜された看視役で、ナチス親衛隊員や看視兵の忠実な部下として、飢餓と病に苦しむ囚人たちをときにはげしく殴打しました。収容所は弱肉強食の道義なき世界で、自分と家族を守るために、暴力や窃盗はもちろんのこと、友人を売ることさえひるまなかったひとたちがいたといいます。
こうした事実をたんたんと記したのち、フランクル博士は次のように述べます。
すなわち、もっともよきひとびとは帰ってこなかった。
2011年3月11日、三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の巨大地震が東日本を襲い、宮城・岩手・福島など太平洋沿岸の広範な地域に甚大な被害をもたらしました。福島第1原子力発電所では、定期点検中の3機を含む6機の原子力発電施設が津波のためすべての非常用電源を喪失しました。
その日の夜、私はあてもなく街をさまよっていました。ネオンの消えた繁華街はひとの姿もまばらで、ときおりすれちがう通行人は、だれもがコートの襟を立て、こわばった表情で家路を急いでいました。
シャッターを下ろした商店街を通り過ぎると、濃紺の深い闇のなかに丈の高い樹々が浮かんでいました。ふだんは恋人たちでにぎわう公園の池の畔にはだれもおらず、高架の先の鉄道駅は照明を落とし、青白い半月に照らされて廃墟のようです。見慣れた世界は突如その様相を一変させ、街は不吉な黒い鳥の影に覆われてしまったかのようでした。
恐怖と得体の知れない高揚がないまぜになったあのときの奇妙な感覚は、いまでもはっきり覚えています。フランクル博士の言葉が、呪文のように、意識の底から何度も繰り返し聞こえていました。
もっともよきひとびとは帰ってこなかった――。
カポーとは、暖房の効いた部屋で、津波に押し流される家や、破壊され焼き尽くされる街をただ眺めていた私のことだったのです。
*
私はこれまで、自由とは選択肢の数のことだと、繰り返し書いてきました。なんらかの予期せぬ不幸に見舞われたとき、選択肢のないひとほど苦境に陥ることになる。立ち直れないほどの痛手を被るのは、他に生きる術を持たないからだ、というように。
私はこのことを知識としては理解していましたが、しかし自分の言葉が、想像を絶するような惨状とともに、現実の出来事として、目の前に立ち現われるなどとは考えたこともありませんでした。
津波に巻き込まれたのは、海辺の町や村で、一所懸命に生きてきたごくふつうのひとたちでした。彼らの多くは高齢者で、寝たきりの病人を抱えた家も多く、津波警報を知っても避難することができなかったといいます。
被災した病院も入院患者の大半は高齢者で、原発事故の避難指示で立ち往生したのは地域に点在する老人福祉施設でした。避難所となった公民館や学校の体育館で、氷点下の夜に暖房もなく、毛布にくるまって震えているのも老人たちでした。
被災地域は高齢化する日本の縮図で、乏しい年金を分け合いながら、農業や漁業を副収入として、みなぎりぎりの生活を送っているようでした。そんな彼らが、配給されるわずかなパンや握り飯に丁重に礼をいい、恨み言ひとつこぼさずに運命を受け入れ、家族や財産やすべてのものを失ってもなお互いに助けあい、はげましあっていたのです。
私がこれまで書いてきたことは、この圧倒的な現実の前ではたんなる絵空事でしかありませんでした。私の理屈では、避難所で不自由な生活を余儀なくされているひとたちは、「選択肢なし」の名札をつけ、匿名のままグループ分けされているだけだったからです。
大震災の後、書きかけの本を中断し、雑誌原稿を断わり、連載も延期して、ただ呆然と過ごしていました。そしてあるとき、まるで天啓のように、それはやってきたのです。
私がこれまで語ってきたことが絵空事であるのなら、その絵空事を徹底して突き詰めることでしか、その先に進むことはできないのではないか――。
理屈でもなく、直感ともいえませんが、この想念は稲妻のように私を襲い、魂を奪い去ってしまったのです。
それから2週間で、この本を書きました。
『大震災の後で人生について語るということ』P204~208
PS 本書は5月の連休明けには脱稿していましたが、本になるまでにすこし時間がかかりました。