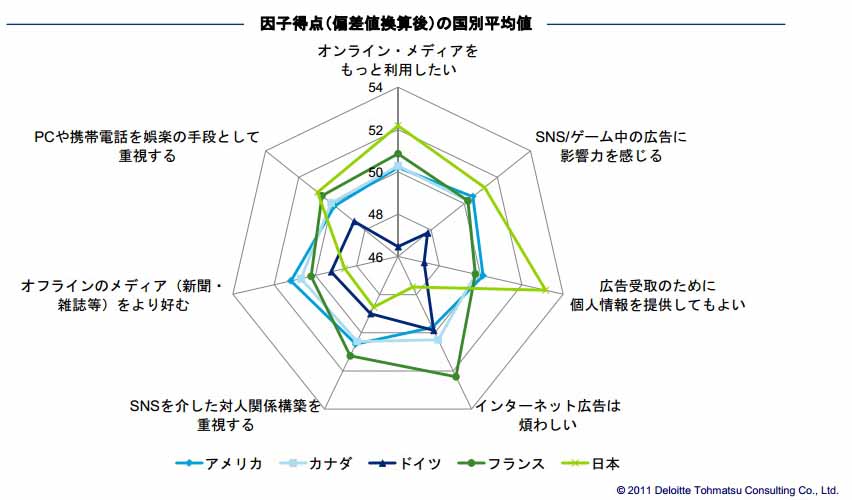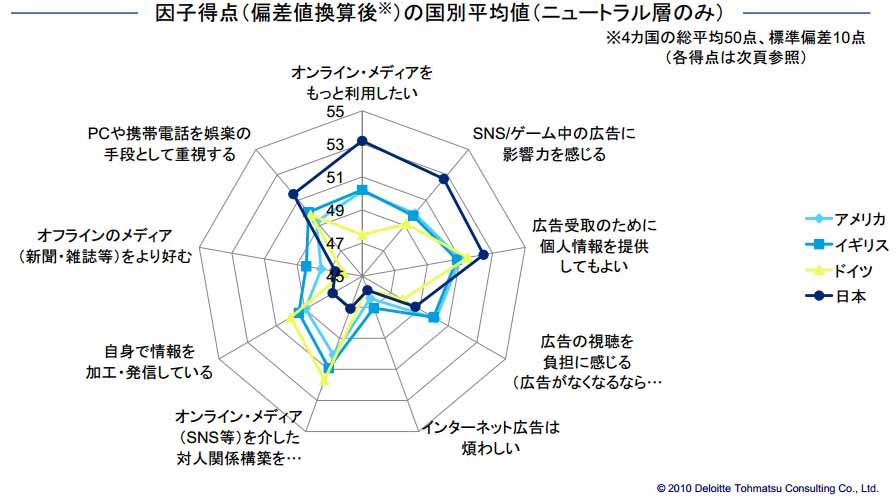カリブ海の島々は、壮大な社会実験のようだ。
キューバはカリブ最大の島で、15世紀末からスペイン人の入植が始まり、砂糖きびプランテーションの労働力としてアフリカから大量の奴隷が送り込まれた。
現在の人種構成はスペイン系とアフリカ系がそれぞれ4分の1で、国民の過半が双方の血を受け継いでいる。子どもたちは全員が公立学校で教育を受け、人種の融合が進んで、肌の色のちがいを意識することはほとんどない。
1959年の革命以来、カストロによる一党独裁の社会主義政権がつづき、街には50年代のアメリカにタイムスリップしたようなクラシックカーが走っている。教育も医療も無料だが、公共交通機関はほとんど機能しておらず、長距離の移動はヒッチハイクするしかない。旧ソ連からの援助がなくなって、いまはすこしずつ経済の自由化に向けて歩みはじめたところだ。
キューバの東にはカリブ海第2の大きさのイスパニョーラ島があり、東側が旧スペイン領のドミニカ共和国、西側が旧フランス領のハイチに分かれている。
ハイチはアフリカ系指導者のもとカリブ海ではじめて独立を勝ち取った輝かしい歴史を持つが、その後の政治的混乱で、現在では北朝鮮やジンバブエなどと並ぶ“失敗国家”の烙印を押されている。それに対してドミニカは、コロニアル建築の残るカリブ海屈指の観光地だ。
グーグルアースで見ると、同じ島なのにハイチとドミニカでは地面の色がちがう。鬱蒼とした熱帯雨林がハイチに近づくにつれてまばらになり、地肌が露出している。貧しい人々が、山の樹々を薪として伐採し尽くしてしまったのだ。
ハイチの悲劇は、隣のドミニカが観光業の優等生になるにつれて、ダークサイドに落ちていったことだ。
独裁や内戦などの混乱の後、政治が安定すると、ドミニカはファミリーに人気のリゾートに変貌した。後れをとったハイチの観光業者は、集客のため麻薬や同性愛を売り物にするようになった。一時は欧米からの観光客で賑わったが、80年代にエイズが蔓延すると社会全体が崩壊してしまったのだ。
2010年の大地震でハイチは30万人を超える死者を出し、その惨状が全世界に報じられた。だがほとんどのひとは、荒廃した最貧国のすぐ隣にゆたかな観光立国あるなどとは思いもしなかっただろう。
ヨーロッパ諸国の植民によって、カリブの原住民は疫病などで死に絶えてしまったから、どこもほぼ同じ条件で国づくりをスタートした。それにもかかわらず、独立から100年あまりでこれほどまで大きなちがいが生じたのだ。
歴史は個人の意志や努力によってつくられるのではなく、偶然の積み重ねだ。生まれた時と場所によって、人生の大半は決まってしまう。それでも私たちは、自分にできることを精一杯やるほかはない。
南の島で、そんなことを思ったのだった。
橘玲の世界は損得勘定 Vol.14:『日経ヴェリタス』2012年3月18日号掲載
禁・無断転載