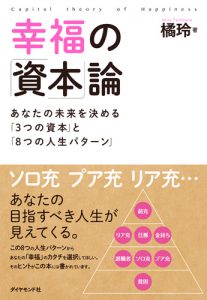アメリカは「超格差社会」だといわている。それがどのような社会なのか、具体的なデータで見てみよう(1ドル=110円で換算/端数は四捨五入)。
まずは所得の比較。アメリカの世帯数は1億6500万で、下位90%の1億5000万世帯の平均所得額は360万円。それに対して上位0.01%=1万6500世帯は32億円で下位90%の900倍になる。
次は資産だが、下位90%の世帯の平均純資産(資産―負債)は920万円。上位0.01%は4000億円でその差はなんと4万倍以上だ。毎年の所得が蓄積されて資産になるのだから、資産格差は所得格差よりもずっと大きくなる。
その結果アメリカでは、下位90%のひとたちが総純資産に占める割合は全体の22.8%しかなく、上位0.01%の超富裕層は資産全体の11.2%を占めている。
上位0.1%の富裕層と比較しても、超富裕層は所得で8倍、資産で9倍ゆたかで、極端な富の集中は明らかだ。このような数字からはアメリカが0.01%によって支配されているように思えてくるし、そのように主張するひとも多い。
しかし視点を変えてこのデータを眺めると、アメリカ社会の別の側面が見えてくる。
所得分布で上位5%以上10%未満では、平均所得額は1600万円だ。資産分布で上位1%以上10%未満では、平均純資産額は1億4000万円になっている。さらに、下位90%と上位10%%を分けるボーダーラインは所得で1300万円、資産で7200万円だから、アメリカでは10世帯に1世帯が所得でも資産でもこれよりゆたかだということになる。
さまざまな幸福の研究では、お金は幸福感に影響するものの、一定額を超えるとそれ以上お金が増えても幸福感は変わらなくなる。暑い夏の日のビールのひと口めはものすごく美味しくても、その感動はだんだん薄れていって、やがて惰性で飲むようになるのと同じだ。経済学でいう「限界効用の逓減」で、ひとの感情はほとんどのことに慣れるようになっているから、お金でもこの法則が通用するのだ。
所得が増えても幸福感が変わらなくなるのはいくらだろうか。これはアメリカで年収7万5000ドル、日本で年収800万円とされていて、奇しくも日米でほぼ同じだ。これは一人あたりなので、世帯ではおおよそ1500万円になる。一方の資産では、金融資産(預金や株式など)が1億円を越えると幸福感が変わらなくなるという研究がある。
幸福の研究では、お金のことを気にすると幸福感が下がることがわかっている。世帯収入1500万円、金融資産1億円というのは、日々の生活でお金のことを気にせず、老後の経済的な不安もなくなる水準なのだろう。
データからわかるのは、アメリカでは上位10%の世帯の大半が、所得でも資産でもこの基準を越えていることだ。「超格差社会」とは、国民の10世帯に1世帯(おおよそ10人に1人)が、「幸福の限界値」を上回るゆたかさを手に入れたユートピアでもある。だからこそ、そこから取り残されたひとたちの絶望がより深まるのだろう。
参考:小林由美『超一極集中社会アメリカの暴走』
橘玲の世界は損得勘定 Vol.68『日経ヴェリタス』2017年6月11日号掲載
禁・無断転載