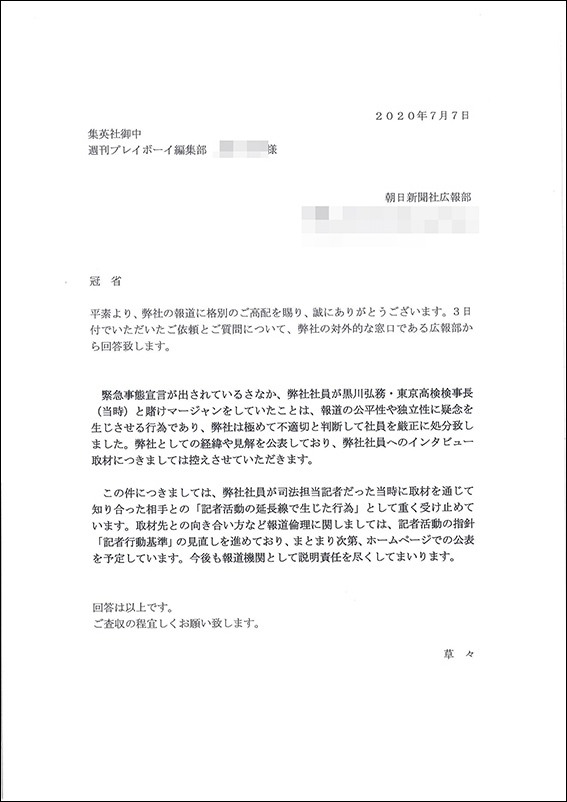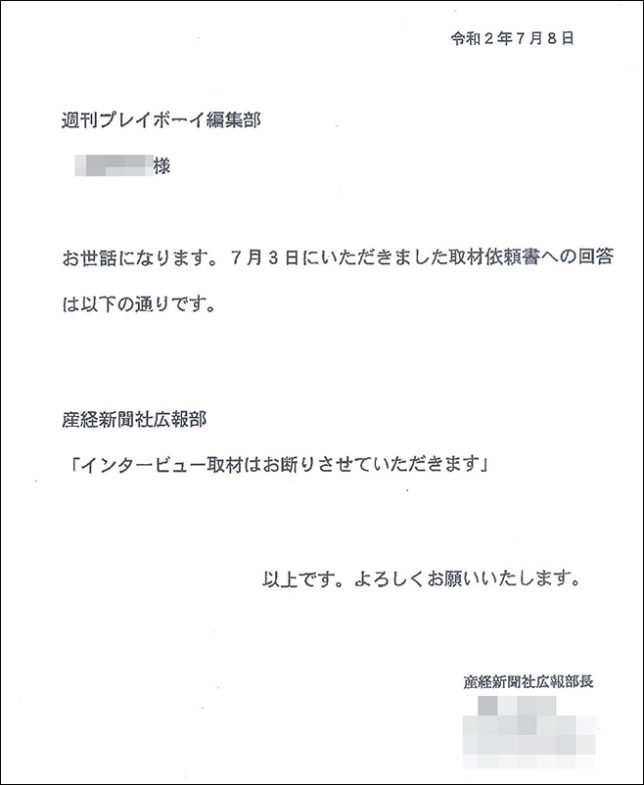経済活動再開を急いだアメリカで新型コロナウイルスの感染者数が記録を更新し、日本も緊急事態は解除されたとはいえ予断を許さない状況がつづいています。とはいえ、欧米で感染爆発が起きたときのような世界的な大混乱が収まってきたことも確かです。そこで、これまでのコロナ禍をいったん「数字」で振り返ってみたいと思います。
「感染のグラウンド・ゼロ」となったニューヨーク州では、3月半ばに200人程度だった1日の感染者は、3月22日のロックダウン開始日に2500人、4月10日は9600人と1万人に迫りました。累積感染者数は7月1日時点で約42万人、累積死者は約3万2000人という驚くべき数字になっています。
ところで、これを100万人あたりに換算すると、感染者は約2万1500人、死亡者は約1700人で、比率はそれぞれ2.15%と0.17%です。さらにこれを逆にするなら、ニューヨーク州民のうち「97.85%は無症状で、99.83%はコロナ禍を生き延びた」ということになります(抗体検査の州全体の感染率は約12%なので、こちらの数字では「88%は感染していない」になります)。
このように、感染者・死者を実数で見るか、比率で見るかで印象はずいぶん変わります。これを行動経済学では「フレームを変える」といいます。
もちろん、500人に1人しか感染症で死なないとしても安心はできません。その1人が自分になるかもしれないからです。知りたいのは全体の平均ではなく、男女、年齢、既往症、居住地などで区分したより詳しいデータでしょう。そのなかから自分にあてはまるカテゴリーを探した方がずっと正確です。
これはたしかにそのとおりですが、実際にやってみるとうまくいきません。ある程度の傾向はわかっても、細分化しすぎると母数が減って統計として意味がなくなってしまうからです。「あなた一人のコロナのリスク」は、ビッグデータは教えてくれないのです。
さらなる問題は検査の精度です。新型コロナの感染を調べるPCR検査は精度が50~70%、(感染していないひとを陽性としてしまう)偽陽性のリスクが1%とされています。6月に厚労省が発表した抗体検査で東京の陽性率は0.1%、1000万人の都民のうち1万人が感染したことになります。
ここで全都民にPCR検査したとすると、精度70%として、1万人の感染者のうち3000人を偽陰性として見逃してしまうことになります。しかしやっかいなのは偽陽性の方で、999万人の非感染者の1%、9万9900人を「感染者」にしてしまいます。検査で「陽性」とされた10万6900人のうち、実際の感染者は6.5%しかいないのです。
感染者と非感染者の数に大きな差があるときに全数検査をすると、偽陽性によって深刻な混乱が起きます。しかし「希望者全員に検査を受けさせろ」と大騒ぎをしていたときに、このことをちゃんと説明したメディアはほとんどありませんでした。――日本は検査体制が整わず結果オーライになったわけですが。
目の前に数字(エビデンス)があっても、示し方次第で判断は大きく変わります。こうして誰もが、「見たいエビデンスだけを見る」ことになるのです。
参考:マイケル・ブラストランド、デイヴィッド・シュピーゲルハルター『もうダメかも 死ぬ確率の統計学』(みすず書房)
『週刊プレイボーイ』2020年7月13日発売号 禁・無断転載