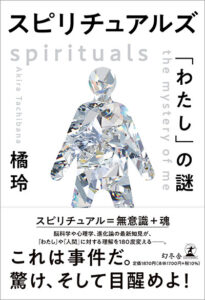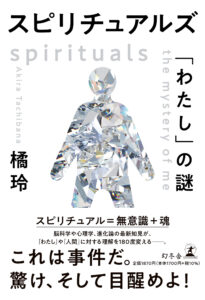出版社の許可を得て、新刊『スピリチュアルズ 「わたし」の謎』の「はじめに」を掲載します。発売日は6月23日(水)ですが、この週末には大手書店の店頭にも並びはじめると思います。
心理学=人間科学でいま、大きなパラダイム転換が起きています。ぜひ私の驚きを共有してください。
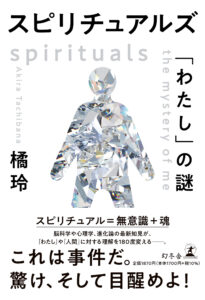
**************************************************************************************
この本では、「わたしは何者か?」という人類史上最大の謎に挑む。
などというと、「なにをバカなことをいってるのか?」と笑われそうだが、これは誇大妄想の類ではない。
近年の脳科学や進化心理学、進化生物学、行動遺伝学などの急速な進歩によって脳=こころの秘密が徐々に明らかになり、いまや「新しいパラダイム」の心理学が登場しつつある。この「驚くべき理論」は人間についての理解を根本的に書き換え、もしかしたらあなたの人生を変えてしまうかもしれない。
それをひと言でいうならば、「わたしもあなたも、たった〝8つの要素〟でできている」になる。
「最先端の科学」といっても難しい理屈が書いてあるわけではない。どの話も、自分やまわりのひとたちに当てはめれば納得できることばかりだろう。「新しいパラダイム」の心理学は、「なぜ自分はこんなふうなのか」「あのひととはなぜわかりあえないのか」など、誰もが漠然と感じていた日常的な疑問に明快にこたえてくれるのだ。
ところでこの理論には、まだちゃんとした名前がつけられていない。心理学のパラダイム転換はさまざまな分野で同時並行的に起こっているので、それを統一的に記述した一般向けの本もほとんどない。だとしたら、誰かがやってくれるのを待つより、自分で書いた方が手っ取り早いと思いついて、「スピリチュアル理論」と名づけることにした。
スピリチュアルというのは、心理学でいう「無意識」に「魂」を重ね合わせた言葉だ。脳科学の知見は、意識が無意識と対立している(あるいは意識が無意識を制御している)のではなく、じつは「わたし」のほとんどすべてが無意識で、意識はその一部(あるいは幻想)でしかないという膨大な知見を積み上げている。「わたし」というのは、突き詰めれば「無意識/魂」の傾向のことなのだ。
わたしたちは一人ひとり異なる複雑で陰影に富む性格(パーソナリティ)をもっているが、それはいくつかの基本的な要素に還元できることもわかってきた。これはパーソナリティ心理学では「ビッグファイブ」と呼ばれていて、「外向的/内向的」「楽観的/悲観的」「協調性」「堅実性」「経験への開放性」のことだ(本書ではこれを8つに拡張している)。その意味では、「わたし」はこれらの要素の組み合わせでしかない。
ここで、「それなら聞いたことがある」とか「性格診断のようなものでしょ」と思ったひともいるかもしれない。
大学などで教えているパーソナリティ心理学では、類型論と特性論から始まって、フロイト流の精神分析学(精神力動論)、ジョン・ワトソンやB・F・スキナーの行動主義、カール・ロジャーズなどの現象学的心理学、マーティン・セリグマンのポジティブ心理学など、パーソナリティに関するさまざまな心理学の流派を網羅的に解説する。「ビッグファイブ」は、そのなかのひとつのエピソードにすぎない。
これから述べることは、それとは
ぜんぜんちがう。
きっかけは、たまたまネットで読んだ記事だった。フェイスブックから大量の個人情報が流出したと大騒ぎしていた頃だから、2018年春だろうか。
その記事によると、フェイスブックの「いいね!」をコンピュータに読み込ませるだけで、それ以外のデータがまったくなくても、どのような人物なのかをきわめて高い精度で予測できるという。その後、頻繁に引用されるようになったインタビューでは、ミハル(マイケル)・コシンスキーというスタンフォード大学准教授が、「このアルゴリズムを使えば10の『いいね!』で同僚よりも相手のことがよくわかるようになり、70の『いいね!』で友人のレベルを超え、150の『いいね!』で両親、250の『いいね!』で配偶者のレベルに達する」と述べていた。
ほんとうにそんなことがあるのか、不思議に思って元の論文を読んでみると、「白人か黒人か」を95%、「性別」を93%、「ゲイ(男性同性愛者)」であることを88%、「(支持政党が)共和党か民主党か」を85%、「キリスト教徒かムスリムか」を82%の精度で予測できたという。「このソフトウエアを使えば、本人が明かしたくないと思っている知能、性的指向、政治的立場などを企業、政府、あるいはフェイスブックの友だちが知ることができる」のだ(*1)。
もっと驚いたのは、フェイスブックの「いいね!」から性格(心理的特性)を予測できることだった。これをSNS(ソーシャルネットワーク)のビッグデータと組み合わせれば、感情的に不安定な(神経症傾向の高い)ユーザーに「安全」を強調した広告を提示するような心理操作が実現可能になる。現実にトランプ陣営は、2016年の大統領選で、コシンスキーの研究に基づいた心理プロファイリングと行動ターゲティングを大々的に行なったのではないかと疑われている。
「いいね!」だけから、あなたが何者かわかってしまう。なぜこんな「魔法」のようなことができるのか。論文によると、「マイパーソナリティ」というフェイスブックのアプリでユーザーに心理テストを行ない、5万8000人あまりの「いいね!」のビッグデータを統計解析(アマゾンやネットフリックスの「おすすめ」に使われているSVD/特異値分解)して、プロフィールや顔写真、知能指数、パーソナリティ、生活満足度、ドラッグの使用履歴などの質問でわかった属性との相関から予測モデルをつくったらしい。──いまならAI(人工知能)にディープラーニング(深層学習)させてより高い精度を実現できるだろう。
このときにコシンスキーたちが使ったのが「ビッグファイブ」で、この「魔法(心理予測モデル)」の中核をなす理論とされていた。そこから興味を感じてあれこれ調べていくうちに、それがとてつもないパワーをもっていることに衝撃を受けた。
ビッグファイブでは、わたしたちの性格(パーソナリティ)を5つの(本書では8つに拡張しているが)要素の組み合わせだとする。このシンプルな理論によって、「わたしは何者なのか?」「わたしとあなたはなぜちがっているのか?」という、人類がずっと抱きつづけてきた疑問が科学として解明できるようになった。
これは控えめにいっても、とんでもない「事件」だ。実際、ビッグファイブを「パーソナリティ研究のルネサンス」「いまや新しい科学が出現しつつある」と述べる心理学者もいる(*2)。「わたし」や「あなた」についての理解を一変させてしまうそのスゴさはとうてい要約できないので、これから(私と同じように)驚いてほしい。
*
脳は長大な進化の過程で、スピリチュアル(呪術的)なものとして「設計」された。
わたしたちにとっての世界(社会)は、「わたし=自己」を中心として、家族、友人、知人、たんなる知り合い、それ以外の膨大なひとたちへと同心円状に構成されている。他者を中心とした世界を生きているひとはいないし、もしいたとしたら精神疾患と診断されるだろう。
ひとの生活は、起きているときと寝ているときに大きく分かれる。眠りに落ちると世界は消え(あるいは夢の世界に変わり)、目が覚めると(現実の)世界が現われる。目を閉じると世界は消え、目を開ければ世界が現われる。
「なにを当たり前のことを」と笑うかもしれないが、この体験はとてつもなく強力だ。スピリチュアル=無意識は(おそらく)、自分が世界の中心にいて、すべてを創造したり、消滅させたりしていると思っているのだ。
わたしたちはみな、人生という「物語」を生きている。スピリチュアルが「神(世界の中心にいる創造者)」なら、人生という舞台のヒーローやヒロインは、当然、自分になるに決まっている。もちろん、すべての男がスーパーヒーローで、すべての女がお姫様を演じるわけではない。社会が複雑になるほどさまざまな物語が生まれ、そこには多種多様な役柄があるだろう。そのなかには「はぐれ者として生きる」「愛するひとを支える」という物語があるかもしれないが、それでもつねに「主役」は自分なのだ。
だとすればパーソナリティとは、スピリチュアル=無意識が創造する「人生という物語」のヒーロー/ヒロインの「キャラ」ということになる。
脳の基本OSは人類共通でも、そのなかのいくつかの傾向は個人ごとにばらつきがある。そのささいなちがいをわたしたちは敏感に察知して、「性格」とか「自分らしさ」と呼んでいる。ビッグファイブというのは、一人ひとりが演じる物語のキャラを〝見える化〟したものなのだ。
*
以下の構成だが、最初に「心理学のパラダイム転換」を理解するうえで必要となる基礎知識をざっと説明する。次に、「ビッグファイブといったって、これまでいろいろ出てきた俗流心理学の亜流で、しょせん一時の流行なんでしょ」というもっともな疑問をもつひとのために(じつをいうと私もそう思っていた)、イギリスの「ケンブリッジ・アナリティカ」という選挙コンサルティング会社のスキャンダルを紹介する。この会社はビッグファイブの心理プロファイリングを使って、2016年にイギリスがEU離脱を決めた国民投票と、アメリカのトランプ大統領誕生に大きな影響を与えた(ある意味、「世界を変えた」)とされる。フェイスブックの「いいね!」から、なぜ人種や性別、性的指向や政治的立場が予測できるかもわかるだろう。
それ以降が本論で、「こころ(無意識)の傾向=特性」を進化的に古いものから説明していく。とはいえ、これはあくまでも私の理解なので、既存のパーソナリティ心理学のビッグファイブ理論とはかなり異なったものになるはずだ。
パーソナリティはビッグファイブ(およびそれ以外の3つの特性)の組み合わせで、現代社会にうまく適応できるものと、適応が難しいものがある。これがいま深刻な社会問題を引き起こしているのだが、最後に「成功するパーソナリティ/失敗するパーソナリティ」としてその概略を述べておきたい。
この地球上には78億人を超えるひとたちが暮らしているのだから、世界には78億の物語があることになる。
それではこれから、スピリチュアルズの世界をともに旅することにしよう。
*1
Michal Kosinski, David Stillwell and Thore Graepel (2013) Private traits and attributes are predictable from digital records of human behavior, PNAS
*2
ダニエル・ネトル『パーソナリティを科学する 特性5因子であなたがわかる』白揚社