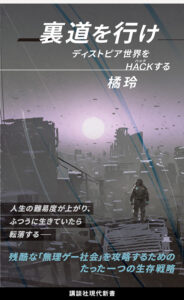アメリカ大統領選の結果を受け入れないトランプ支持者が連邦議会議事堂に乱入・占拠するという前代未聞の混乱で幕を開けた2021年も、残すところあとわずかになりました。
日本では8月にコロナの感染拡大で医療が逼迫、患者が次々と自宅で死亡したことで、菅前総理は総裁選の出馬を断念しました。ところがその後、なぜか感染者数が急激に減りはじめ、それを追い風に「新しい資本主義」を掲げる岸田自民党が総選挙を制し、いつもと変わらない日本政治の風景が続いています。
今年最大のイベントは東京五輪で、それなりに盛り上がったものの、大リーグ大谷翔平選手の活躍によって、いまではひとびとの記憶も薄れつつあるようです。五輪関連で強い印象を残したのは、開会式の演出にかかわったアーティストや演出家の過去の言動がSNSで炎上し、次々と辞退(キャンセル)に追い込まれたことでしょう。欧米ではこれは「キャンセルカルチャー」として10年ほど前から問題視されていましたが、世界の潮流から一周遅れで、いよいよ日本にもその大波が到来したことになります。
キャンセルカルチャーは「社会正義」を求める左派(レフト)の運動で、攻撃の対象になるのは人種差別や性差別にかかわったとされる者です。ところが日本では、結婚問題をめぐって、皇族とその婚約者が大々的な「キャンセル」の標的になるという前代未聞の事態が起きました。
ヒトの脳は「下方比較」を報酬、「上方比較」を損失と感じるように進化の過程で設計されており、自分より上位の者を引きずり下ろすことで大きな快感が生じます。SNSは「正義」の名の下に、ゼロコストかつ無リスクでこの快感を手に入れる方法をすべてのひとに提供しました。日本や世界で広がる混乱は、この生理学的な仕組みでおおよそ説明できるでしょう。
8月には小田急線の電車内で36歳の男が刃物を振り回し、乗客10人が重軽傷を負う事件が起きました。男は車内に灯油をまいて火をつけようと計画したものの入手できず、常温では発火しないサラダ油で代用し、からくも大惨事をまぬがれました。
加害者の男は大学を中退したあと「ナンパ師」をしていましたが、やがて無職になり生活保護を受けていたとされます。男が最初に狙ったのは、「勝ち組っぽく見えた」20歳の女子大生でした。
この事件に続いて10月のハロウィンの夜に、京王線の特急列車内で、「バットマン」の悪役ジョーカーの仮装をした24歳の男が、72歳の男性をナイフで刺したあと、ライターオイルを床に撒いて火をつけ、18人が重軽傷を負う事件が起きました。年下の恋人と破局し、バイト先で客のシャワールームを盗撮しようとするなどのトラブルを起こし、コールセンターの仕事を辞めたあと、大量殺人で死刑になることを考えたと供述しています。
その一方で、電気自動車のテスラやロケット開発のスペースXの創業者であるイーロン・マスクの個人資産が30兆円を超え、従業員7万人(連結従業員36万人)のトヨタの時価総額に並びました。。「上級国民/下級国民」というネットスラングが現実化した気の遠くなるような落差も、今年を象徴する出来事でしょう。
『週刊プレイボーイ』2021年12月20日発売号 禁・無断転載