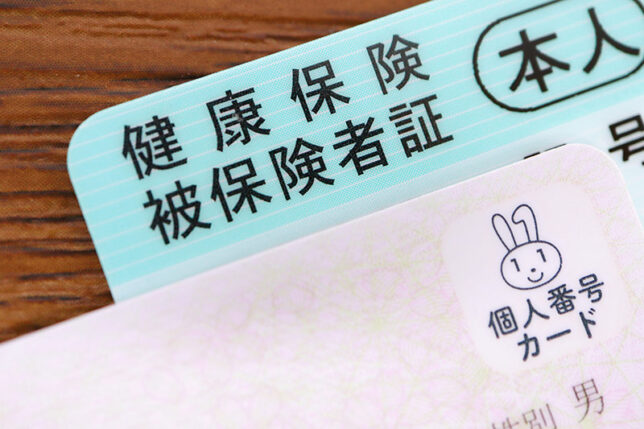ダイヤモンド社と共同で行なっていた「海外投資の歩き方」のサイトが終了し、過去記事が読めなくなったので、閲覧数の多いものや、時世に適ったものを随時、このブログで再掲載していくことにします。
今回は2018年9月13日公開の「黒人保守派のソーウェルが アファーマティブ・アクションを否定する理由」です。(一部改変)

******************************************************************************************
2018年8月30日、アメリカ司法省はハーバード大学の入学選考でアジア系の学生が不当に排除されているとの意見書を提出した。
ハーバード大が2013年に行なった学内調査では、学業成績だけならアジア系の割合は全入学者の43%になるが、他の評価を加えたことで19%まで下がった。また2009年の調査では、アジア系の学生がハーバードのような名門校に合格するには、2400点満点のSAT (大学進学適性試験)で白人より140点、ヒスパニックより270点、黒人より450点高い点数を取る必要があるとされる。
米司法省の意見書は、「公平な入学選考を求める学生たち(SFA)」というNPO団体が、ハーバード大を相手取って2014年にボストンの連邦地裁に起こした訴訟のために提出されたもので、同団体は白人保守派の活動家が代表を務めている。トランプ大統領に任命された共和党保守派のジェフ・セッションズ司法長官も、「誰も、人種を理由に入学を拒否されるべきではない」と述べた。こうした背景から、今回の意見書は、白人に対する「逆差別」として保守派が嫌悪するアファーマティブ・アクション(積極的差別是正措置)撤廃に向けての布石ともいわれている(「「ハーバード大、アジア系を排除」米司法省が意見書 少数優遇措置に波及も」朝日新聞2018年9月1日)。
「アンクル・トム(白人に媚びを売る黒人)」と呼ばれて
奴隷解放宣言100周年の1963年、マーティン・ルーサー・キングは「私には夢がある(I Have a Dream)」の有名な演説のなかで、「肌の色でなく人格の中身によって」認められる社会を目指そうと訴えた。これが「カラー・ブラインド主義」で、当たり前のことだと思うかもしれないが、その後、アメリカ社会に大きな混乱をもたらすことになる。なぜならアファーマティブ・アクションでは、公的機関の雇用や公共事業の入札、大学への入学枠などで、「肌の色」による優遇(差別是正)が行なわれているからだ。
これに対して「逆差別」される側の白人やアジア系から不満が出るのは当然だが、じつは黒人のなかにも「アファーマティブ・アクションを廃止すべきだ」と主張する一派がいる。彼らは「黒人保守派」と呼ばれ、アメリカ政治のなかでは特異な地位を占めているが、その根拠はキングの「私には夢がある」の一節だ。「肌の色でなく人格の中身によって」国民を平等に評価するのなら、大学への入学も人種に関係なく(カラー・ブラインドで)得点のみで決めるべきだ、となるほかない。
黒人保守派としては、日本ではシェルビー・スティールの『黒い憂鬱 90年代アメリカの新しい人種関係』(李隆訳/五月書房)などがよく知られている。
スティールは1946年に、シカゴでトラック運転手をしていた黒人の父親と、ソーシャルワーカーだった白人の母親のあいだに生まれた。大学で政治科学や社会学を学んだあと、ユタ大学で英語学の博士号を取得し、サンノゼ州立大学で英文学を教えたのち、フーバー研究所のフェローとなった。双子の兄弟のクラウド・スティールも学者で、スタンフォード大学教育学部長などを務めた。
こうした経歴からもわかるように、「肌の色を気にせずにすむ社会」を目指す黒人保守派は典型的なエリートで、白人保守派から支持される一方、黒人活動家やリベラル派の白人からは「アンクル・トム(白人に媚びを売る黒人)」の蔑称で毛嫌いされている。
経済学者のトーマス・ソーウェルはスティールと並ぶ黒人保守派の代表的な論客だが、日本ではほとんど知られていない。唯一『入門経済学 グラフ・数式のない教科書』 (加藤寛監訳、堀越修訳/ダイヤモンド社)が翻訳されているが、これは「専門用語を使わず、さらに関数もグラフも登場しないため、経済学に必須の数学が苦手な人でも十分理解できる」経済学の入門書で、手に取ったひとはソーウェルの政治的立場はもちろん、黒人であることもまったく気づかないだろう。
黒人保守派はなぜ、公民権運動で勝ち取った黒人の権利を放棄するような主張をするのだろうか。それを知りたくて、ソーウェルの自伝“A Personal Odyssey(私の人生航路)”を読んでみた。以前紹介した“The Idealist”と同様にとても面白い本だが、本書も同様に翻訳されることはなさそうなので、この機会に紹介してみたい。