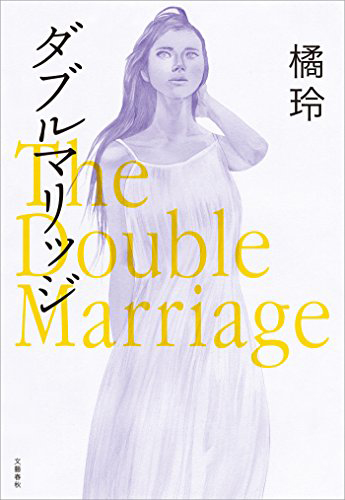2016年に国際社会を揺るがした最大の事件は、イギリスのEU離脱を決めた6月の国民投票だと思っていたら、11月のアメリカ大統領選でそれを上回る衝撃が起きました。もうひとつの驚きはAI(人工知能)で、ディープラーニングによってコンピュータがチェスだけでなく、より複雑な将棋や囲碁でプロを圧倒する時代がやってきました。
じつはこのふたつの出来事は、「知識社会化」という同じコインの裏表です。
『ワイアード』創刊編集長のケヴィン・ケリーは、人間がテクロジーを開発しているのではなく、テクノロジーが人間を利用して自ら進化しているのだという「テクニウム(テクノロジー生態系)」を唱えました。テクノロジーはまるで生物のように、さまざまな知を吸収して未知の領域へと自己組織化していくのです。
社会が高度に知識化すれば、それに適応するにはより高い知能・技能が求められます。――パソコンを使いこなせないと事務の仕事すらできない、というように。仕事に必要とされる知能のハードルが上がれば、必然的に多くの労働者が仕事を失うことになるでしょう。これが「格差社会」とか「中流の崩壊」と呼ばれる現象です。
しかし失業したブルーワーカーは、なぜ自分が虐げられるのかがわかりません。その怒りを動員するのがポピュリストの政治家で、今年はフランスやイタリア、ドイツなどでも同じ光景を見ることになるでしょう。なぜなら、知能の格差が経済格差を生み、社会を混乱させるのは、(新興国との競争にさらされる所得の高い)先進国に共通の問題だからです。
AIがその驚くべき能力を示しはじめたとき、多くのひとが、人間がロボットに支配されるSF的なディストピアを予感しました。しかしその後、すこし冷静になると、AIは人間に取って代わるものではなく、人間の知能を拡張するツールだといわれるようになりました。脳(身体)とコンピュータは仕組みが本質的に異なっているので、AIがどれほど学習しても、人間のような認知能力や共感能力を持つことはできないからです。
しかしこの事実も、あまり明るい未来は見せてはくれません。
AIが知的能力を大きく引き上げるとしても、それはすべてのひとに平等に恩恵を与えるわけではありません。そこからもっとも大きな利益を得るのが、高度で複雑なテクノロジーを効果的に使いこなす、知的能力の高いひとであることは間違いないからです。同様のことはビッグデータ(統計解析)などの分析手法や、ビットコイン(ブロックチェーン)、3Dプリンタ、VR(ヴァーチャル・リアリティ)のような新しい技術にもいえるでしょう。
このようにしてテクノロジーの「進化」がますます知能の格差を広げ、それによって富は局在化し、経済格差が深刻になり、社会は分断されていきます。これは知識社会化がもたらす必然ですから、人類がこの運命を避けることは(おそらく)できないでしょう。
だとすれば、私たちはどうすればいいのでしょうか。
そのこたえを私は持ち合わせませんが、ひとつだけ確かなことがあります。それは、「経済格差は知能の格差」という現実から目を背けるなら、私たちはグロテスクな「陰謀論」の世界に落ちていく以外の未来はない、ということです。
参考:ケヴィン・ケリー『テクニウム――テクノロジーはどこへ向かうのか?』
『週刊プレイボーイ』2017年1月5日発売号 禁・無断転載