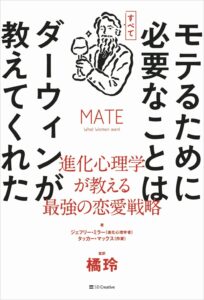本日発売のタッカー・マックス、ジェフリー・ミラー『モテるために必要なことはすべてダーウィンが教えてくれた 進化心理学が教える最強の恋愛戦略』の監訳者まえがきを、出版社の許可を得て掲載します。
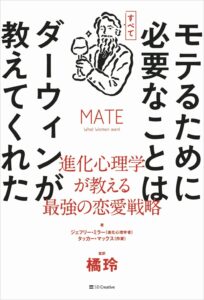
******************************************************************************************
誰でも、「若いときに知っていれば人生が変わったのに!」と思うことがあるだろう。これはまさにそのような本だ。
君が10代、あるいは20代でこの本を手に取ったのなら、ものすごくラッキーだ。30代や40代で、新しい出会いを求めているときにも十分役に立つだろう。
男の子の親が本書を読めば、難しい性愛の話を子どもにどのように伝えればいいかわかるだろう。女性の読者でも、自分の恋愛に新たな気づきを得られるはずだ。
なぜこれほど万能なのかというと、これが進化論的に書かれた「モテ本」だからだ。
男も女も、数百万年の人類の進化のなかで、類人猿や霊長類を加えれば数千万年の歴史のなかで、脳(感情や意思決定)のプログラムを徐々に更新してきた。
ヒトはそれにくわえて文化的・社会的な影響を強く受けているが、それでもOS(オペレーティングシステム)は旧石器時代からたいして変わっていない。生殖は生存と並んで生きもの(より正確には「利己的な遺伝子」)にとってもっとも重要で、男と女のモテのOSには、時代や国、文化などを超えた普遍性(ヒューマンユニヴァーサルズ)がある。
OSやプログラムの仕組みがわかれば、それを解析することでモテに活用できる。
このように書くと、「それってよくあるナンパ本じゃないの?」と思うだろう。だが著者たち(とりわけ進化心理学者のジェフリー・ミラー)は、女の脳をリバースエンジニアリング(逆行解析)することでナンパし、女性に点数をつけてベッドに連れ込んだ合計点を競うようなPUA(ピックアップ・アーティスト/ナンパ師)の手法を批判するために本書を世に問うた。なぜなら、PUAの俗流進化論は(ほとんど)デタラメだから。
「リベラル」な知識人は、「進化論を安易に人間に適用してはならない」「ヒトは遺伝と文化の共進化でつくられてきたのだから、生物学だけでは何もわからない」などの理屈を好む。それに対して本書は、生物学、遺伝学、社会学、人類学、心理学などの最新の知見を縦横に駆使して、より徹底的に進化論を突き詰めることでモテの本質に迫ろうとする。
著者たちの主張はきわめて明快だ。
① 女性の性愛の選択は進化の過程でどのように「設計」されてきたのか。
② 女性が(無意識に)魅力を感じる「特性」にはどのようなものがあり、それをどう身につけるか。
③ その特性をどうやって効果的に「シグナリング(宣伝)」するか。
──の順にクリアしていけば、ごく自然にモテるようになる。ここで展開される生物学的な論理に反発することもあるかもしれないが、最後には誰もが実体験に照らして深く納得するだろう。
「男も女も後世に残す遺伝子を最適化するためのヴィークル(乗りもの)にすぎない」という冷徹な現代の進化論が、道徳的・倫理的に女の子にモテるようになるにはどうすればいいのか、さらには、よりよく生きるとはどういうことかという熱い議論につながっていくアクロバティックな知の冒険が本書の最大の魅力だ。
著者たちについて簡単に説明しておこう。
1965年生まれのジェフリー・ミラーは気鋭の進化心理学者で、ニューメキシコ大学准教授。メイティングMating(ヒトのつがい行動)の進化論的起源を探る研究で知られ、2008年には、「排卵期のラップダンサーはより多くのチップを稼ぐ」という研究でイグノーベル賞の経済学部門を受賞した。主著『恋人選びの心 性淘汰と人間性の進化』(岩波書店)、『消費資本主義! 見せびらかしの進化心理学』(勁草書房)は共に翻訳されている。
1975年生まれのタッカー・マックスは、シカゴ大学を飛び級で3年で卒業したあと、デューク大学のロースクールを修了したものの法律の道へは進まず、ブログにパーティやバー、クラブでの破天荒な体験を書いて人気を博した。
著作は翻訳されていないが、『I Hope They Serve Beer in Hell(地獄でビールを出してくれればいいのに)』はニューヨークタイムズのベストセラーリストに掲載され、世界じゅうで200万部を売り上げた。『Assholes Finish First(クソ野郎が一番になる)』などほかの著書も100万部以上を売り上げ、アメリカ流のパーティカルチャーを背景に新しい青春文学を創造したと評価される人気作家だ。
その経歴からわかるように、マックスはPUA用語で「アルファ」「ナチュラル」と呼ばれる天性の「モテ」で、メソッドにはいっさい頼らず100人を超える女性とのセックスを経験した。どんなパーティでも目立つ華やかさとユーモアのセンスがあり、魅力的な女たちが向こうから集まってくるのだ。だがその後、「酒とバラの日々」からはあっさり足を洗い、趣味のクロスフィット(短時間・高強度のワークアウトを行なうフィットネス)のジムで知り合った女性と結婚し、テキサス州オースティンで妻と3人の子どもたちと暮らしている。
本書では、進化心理学者としてのミラーの知見をマックスの実体験で検証することで、学者による机上の空論ではない数々の「使えるモテのアドバイス」が提案されている。その根幹は女性の脳の進化的なプログラムにアピールすることだから、もちろん日本でもそのまま適用できるだろう(この本に書いてあることを理解し、実行すればモテるようになる)。
「政治的な正しさ(ポリティカル・コレクトネス)」にしばられていると、本当に大事なことを見失ってしまう。そしてほとんどの場合、努力はたんなる時間の無駄で終わる。恋愛やセックスの「きれいごと」をすべて破壊し、事実だけにもとづいて展開される「進化論的に正しい」モテ本の登場に、ぜひ一緒に驚いてほしい。
なお、本書は原書の全訳(それだと600ページを超える大著になってしまう)ではなく、日本の読者向けに再構成している(詳細については「監訳者あとがき」を参照されたい)。PUAについては『裏道を行け ディストピア世界をHACKする』(講談社現代新書)で書いたので、併せて読んでいただければ著者たちの立場がより理解できるだろう。
橘 玲