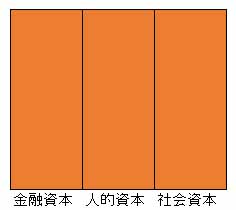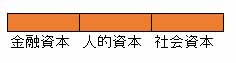昨年末に『「読まなくてもいい本」の読書案内』を出版して、「これまでとテーマが変わったんですか?」との質問が寄せられたので、新年ということもあり、私のなかでどのようにつながっているのかをちょっと説明したいと思います。
これまで何度か述べてきたことですが、「私たちがこの世界に生まれ、いまを生きているということがひとつの奇跡であり、限られたその時間をできるだけ有効に使うには人生を正しく(合理的に)設計しなければならない」というのがすべての前提です。
私たちは金融資本、人的資本、社会資本という3つの資本から富(ゆたかさ)を得ています。
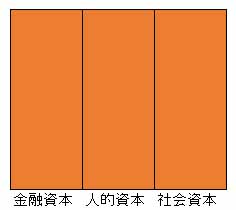
これらの資本をすべて失ってしまった状態が「貧困」です。
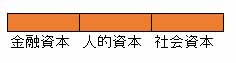
これら3つの資本のなかで、金融資本は、金融市場から富を獲得するための投資理論としてモデル化されています。
金融市場についての理論には、経済学の効率的市場仮説と、それを批判したベノワ・マンデルブロのフラクタル理論があります。効率的市場仮説(モダンポートフォリオ理論)は市場を正規分布(ベルカーブ)と統計学で把握しようとするもので、それに対してマンデルブロは、市場はべき分布(ロングテール)の複雑系で、統計的には予測不可能な出来事(ブラックスワン)が頻繁に起こると述べました。いずれも理論の骨格は1980年代にすでに完成しており、30年間、新たなブレークスルーはありません。
さらにいうと、ブラック=ショールズ式によってオプション価格が計算可能になったのは1970年代前半で、それ以降、40年にわたってデリバティブ(先物、オプション、スワップ)を超える金融商品は開発されていません(テクノロジーの進歩によってデリバティブの種類は増えました)。
金融資本については標準的な理論がすでに定まっているので、それをどのように有効活用すべきかという議論が可能です。それ以前に、金融市場から獲得する「富」とは金銭のことなので、話がものすごくシンプルです。リスクが同じなら、より多くの利益を見込めるのがよい投資戦略なのです。-ーこれが最初に金融資本(金融市場)を取り上げた理由です。
金融市場への投資と同様に、私たちは人的資本を労働市場に投資して富を獲得しています。こうした見方を最初に提唱したのは経済学者のゲイリー・ベッカーですが、ベッカーはその際、労働市場の「富」を金融市場と同じく金銭に換算できると考えました。同じ労働時間であれば、より大きな報酬を得られるようにするのが人的資本の有効活用なのです。
この簡略化によって人的資本を経済学的に分析できるようになったのですが、すぐにわかるように、これは私たちの「はたらく」という実感とはかけ離れています。私たちは労働から、金銭以外の「生きがい(内発的動機づけ)」も得ているからです。お金はもちろん大切ですが、人的資本理論の枠組だけでは「はたらく」ということをうまく説明できないのです。
「好きなことを仕事にしたい」とか、「イヤなこと(ムダなこと)をやりたくない」というのは、誰もが共通に望むことでしょう。そこで、日本社会の制度の歪みから人的資本をもっとも効果的に活用する戦略として提案したのが「マイクロ法人」ですが、これは形式的な方法論なので、内容(なにをすべきか)についてこたえるものではありません。
社会資本とは人間関係のことで、社会的動物としての私たちは家族や友人、仕事仲間などから多くの「富」を得ていますが、これは人的資本よりもさらに金銭への換算が困難です。社会資本における「富」とは、幸福のことだからです。
人的資本や社会資本の金銭に換算できない部分はこれまで、成功者の人生訓や宗教で説明されてきました。これをアカデミズムの領域で扱うのが心理学、社会学、哲学などの人文社会科学ですが、そこに統一的な理論があるわけではなく、それぞれのタコツボ的な学問分野のなかで恣意的に語られてきただけです。
ところが20世紀後半から、この分野に大きな知のパラダイム転換が起こりました。これが「現代の進化論」を基礎とする複雑系、ゲーム理論、脳科学、分子遺伝学、統計学(ビッグデータ)などの諸分野で、旧来の人文社会科学はこうした自然科学の侵食を受けてどんどん使いものにならなくなっています。
新しいパラダイムの最大の特徴は、「科学」として、仮説を実験や観察によって検証可能なことです。これによって、タコツボと化した「文系」の学問を統一的な理論によって議論することがはじめて可能になりました。これは知の世界におけるとてつもない衝撃で、日本ではまだ広く受け入れられているとはいえませんが、今後10年のうちに誰の目にも明らかになるはずです。
私たちは幸福になることを目指して生きていますが、幸福は抽象的な概念ではなく、怒りや悲しみと同様に、進化の過程のなかでつくられてきた感情です。「幸福の理論」としての人的資本や社会資本は、哲学や心理学、社会学などの互換不可能な恣意的な理論ではなく、一般化可能な「新しいパラダイム」に則って論じるべきです。
とはいえいきなりこんなことをいっても理解してもらうのは難しいので、その前段階として、いま知の最前線でなにが起きているのかを誰でも(高校生でも)わかるような本が必要でした。ところが日本では、(それぞれの分野におけるレベルの高い入門書はたくさんあるものの)こうした全体像を俯瞰できる手頃な本がこれまでなかったので、次のステップへと至るためにまずはそれを書くことにした、ということです。
私の考えをかんたんにいうと、「金融資本は分散投資し、人的資本は(好きなことに)集中投資する」のが基本戦略です。人的資本は社会資本(評判)につながっていて、より大きな社会資本から私たちは「幸福」を感じることができます(ただし、あまりにも評判が大きくなりすぎるとプレッシャーに押しつぶされたりします)。
それに対して金融資本から得られる効用は、蓄積が少ないときは一気に逓増しますが、一定額を超えると急速に逓減してしまいます。--フェイスブックのCEOマーク・ザッカーバーグは、保有する資産の99%を慈善活動に寄附すると表明しました。
超高度化した知識社会において(知の)イノベーションを起こせるのはシリコンバレーだけで、グーグルやアップル、アマゾン、フェイスブック(あるいは次世代の新興企業)がビジネスインフラ(プラットフォーム)のデファクトスタンダードを競いあっています。それを利用することで、自営業者やマイクロ法人、家族経営の小企業が旧来の大企業と互角のビジネスができるようになる未来がもうすぐやってきます。大企業のメリットは分業の効果を最大化することですが、その反面、大きな管理コストが必要になるため、今後は徐々にそのアドバンテージを失っていくでしょう。
同時に、サイバー化した現代では、私たちを取り囲む世界は、家族や恋人などの最小単位の人間関係と、ネット上の世界大の仮想コミュニティへと二極化していくのではないでしょうか。「知のパラダイム転換」につづいて、こうした「社会のパラダイム転換」がやってくることを前提として人生設計を考える必要があります。
というようなことが私の頭のなかで『「読まなくてもいい本」の読書案内』につながっているのですが、最後に断っておくと、ここから普遍的な「幸福の理論」に到達できる楽観的な見通しを持っているというわけではありません。
PS Amazonに寄せられた書評のほとんどがKindle版での購入になっていることが、もうひとつの「パラダイム転換」ではないかと今回思いました。