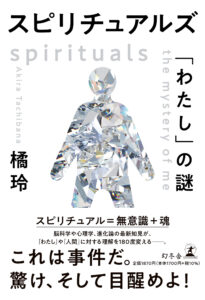出版社の許可を得て、新刊『スピリチュアルズ 「わたし」の謎』の「あとがき」を掲載します。本日発売です。
****************************************************************************************
私はもともと、心理学の「性格診断」などというものをまったく信用していなかった。その考えを改めざるを得なくなったのは、ドナルド・トランプが当選した2016年の米大統領選をきっかけに、「SNSのビッグデータをAIに読み込ませるだけで有権者のパーソナリティが分析できる」「10の『いいね!』を見るだけで同僚よりも相手のことがよくわかるようになり、70の『いいね!』で友人のレベルを超え、150の『いいね!』で両親、250の『いいね!』で配偶者のレベルに達する」という驚くべきファクトを突きつけられたからだ。
それから、なぜこのような不思議なことが起きるのかを調べはじめた。本書はそこから得た知見をまとめた最初の試みで、これから何冊か「心理学のパラダイム転換」についての本を書いてみたいと考えている。
私はこれまで1年のうち3カ月ほどを海外で過ごしてきたが、未知の感染症によって旅に出ることはできなくなった。本書は、自宅と仕事場をひたすら往復する日々のなかで書き進めたものだ。
その作業のなかで、自分のパーソナリティをよりはっきりと理解できるようになった。
まず、私の内向性パーソナリティは平均より高い。五感が他人より敏感ということはないが、賑やかなところは苦手で、パーティなどにもほとんど出席しない。とはいえ、知らないひとと話をするのが嫌いというわけではなく、編集者時代は、のちに日本国の総理大臣になる政治家からヤクザの親分まで、面白そうなひとには片っ端から会いに行った(オウム真理教のサティアンも取材で訪れた)。
内向性スコアが高いと依存症になりにくいというが、たしかになにかにこだわるということはない。ギャンブルにはまったく興味がないし、若いときに吸っていたタバコもさしたる苦労もなくやめられた(イランを旅したときは、アルコールのない環境にすぐに順応できた)。所有や収集への欲求もほとんどなく、別荘はもちろんマイホームやマイカーももっていない。
新型コロナでわかったもうひとつの内向性のメリットは、他者との接触を避ける「新常態」に向いていることだ。この1年、家族以外とはほとんど対面で会わなかった(Zoomでの打ち合わせやインタビューはあった)が、それをストレスに感じたことはない。
抑うつ的になったことはあまりないので、神経症傾向はさほど高いわけではないだろう。だが楽観的かというとそんなことはなく、最後はどこかで野垂れ死ぬだろうと思っているところはある。本書も含め、自分が書くものに「抑うつリアリズム」が強く反映していることもわかっている。
社会に反抗するようなことはないが、中学生の頃から組織のなかでうまくやっていけそうにないことは自覚していた。サラリーマン経験はあるものの10年ちょっとで、いまはもの書きという自営業をしているのだから、同調性は他人より低いだろう。
共感力は女性よりは明らかに低いが、男性の平均程度ではないかと思っている(そもそも共感力の高い男というのをあまり見たことがない)。Qの尻尾は左側に書くタイプだ。
堅実性は、もの書きになってから原稿の締め切りをいちども遅らせたことがないので、高い方ではないかと思う。ただし、意味がないと思うことでもこつこつやる、ということはまったくない。
知らない土地を旅して、自分とはちがうひとたちと出会うのが面白いと思っているので、経験への開放性は平均より高いのではないか。芸術的なセンスはないが、みんなが話題にしているものには関心がない、という傾向はある。
読者も、本書から同じように、自分のパーソナリティについてなんらかの気づきを得られたのではないだろうか。自分を知ることが大事なのは、けっきょく、自分がもっているものでなんとかやっていくしかないからだ。
*
近年の「コネクトする脳」仮説では、ヒトの脳は「つながる」ように設計されていると考える。徹底的に社会的な動物であるヒトは、ごく自然に他者と交流し、助け合い、競争する。そればかりか、わたしたちはイマジネーション(想像力)によって、祖先や歴史上の人物、アニメやマンガ、ゲームなどのヴァーチャルなキャラとも「つながる」ことができる。わたしもあなたも、客観的には、時空を超えた巨大なネットワーク(世界)のひとつのノード(結節点)に過ぎない。そのきわめて小さなノードの一つひとつが、主観的には〝神〟だと錯覚しているところに、人生のよろこびと絶望があるのだろう。
この本は、そんなスピリチュアルをテーマにした当初の構想の前半にあたる。私の理解では、心理学におけるもうひとつのパラダイム転換は、「無意識は自らの死すべき運命を拒絶しようとしている」という「死の回避(存在脅威管理)理論(*1)」で、後半はそれに基づいて宗教や神秘主義などスピリチュアリティを論じたいと思っていたのだが、そうなると分量が大幅に増えていつ完成するかわからないので、残念だが次の機会にしたい。本書は、『残酷な世界で生き延びるたったひとつの方法』『(日本人)』(ともに幻冬舎文庫)に続く三部作として読んでいただければと思う。
私の他の著作と同様に、本書のベースにあるのは進化論だ。思想や感情が脳の産物である以上、それは長大な進化の過程で、生存や生殖を最適化するために「設計」されたプログラムと考えるほかはない。驚異的なテクノロジーの進歩を背景に、将来的には、人間や社会に関する学問分野はすべて進化論に収斂していくはずだし、事実、心理学、社会学から政治学や経済学(あるいは哲学、宗教学)に至るまで、人文科学系の学問は脳科学や遺伝学、進化生物学、進化心理学、ゲーム理論などの自然科学に侵食され吸収されつつある。日本の「文系知識人」の多くはいまだにこのことに気づいていないようなので、あえて指摘しておく(*2)。
わたしたちは誰もが、スピリチュアル=神として、自分だけの物語を生きている。これは、人類が数万年、あるいは数十万年前に自己(過去から未来へとつづく物語)を獲得したときに運命づけられたのだろう。それは祝福でもあり、呪いでもあった。
78億の物語は重なりあって共鳴し、ときに熱狂を生むとしても、本来は別々のものだ。わたしとあなたの物語が完全に重なりあうことはなく、孤独はつねに人生とともにある。
「自分さがし」というのは、突き詰めて考えるなら、自分のキャラ(パーソナリティ)とそれに合った物語を創造することだ。おそらくは、人生にそれ以外の意味はないのだろう。
*1
アーネスト・ベッカー『死の拒絶』平凡社、シェルドン・ソロモン、ジェフ・グリーンバーグ、トム・ピジンスキー『なぜ保守化し、感情的な選択をしてしまうのか 人間の心の芯に巣くう虫』インターシフト
*2
詳しくは拙著『「読まなくてもいい本」の読書案内 知の最前線を5日間で探検する』(ちくま文庫)を参照されたい。