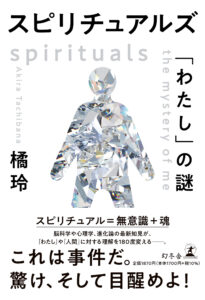ネット上には膨大なフェイクニュースが飛び交い、それが社会に大きな影響を与えることが無視できなくなってきました。
アメリカではQアノンが、「コロナのワクチンにはマイクロチップが入っていて、5G電波で操られる」などの陰謀論を唱え、ワクチン接種が進まない理由になっています。このワクチン陰謀説は世界的に広まっており、日本でも県議会議長を務めた自民党県連の重鎮が「(ワクチンを打てば)5年で死ぬ」などと主張していることが報じられました。
こうした誤情報に対抗する武器とされるのがファクトチェックです。「間違った信念は科学的に正しい情報を与えることによって訂正されるはずだ」というのは、至極もっともに思えますが、はたしてこの常識はどこまで通用するのでしょうか?
アメリカの研究者が、「誤情報の訂正にひとはどのように反応するのか」を調べた研究があります。
2001年の同時多発テロで、ブッシュ政権はイラク(サダム・フセイン)が大量破壊兵器を保有していることを理由に開戦に踏み切りました。ところがのちに、イラクには大量破壊兵器は存在しないことが明らかになりました。
研究者はこれを利用して、リベラルと保守で政治的立場が異なる被験者に、ブッシュ大統領がイラク戦争を熱烈に擁護している記事と、その後の訂正記事(大量破壊兵器はなかった)を読んでもらいました。
リベラルな被験者は、もともとブッシュの演説に同意する割合が高くなかったのですが、その根拠が間違っていたことを知ったあとは、イラク戦争の正当性への疑念がさらに高まりました。ファクトチェックによって正しい認識をするようになったのですから、これはよいことです。
ところが保守的な被験者では、まったく予想外のことが起こりました。このひとたちもファクトを呈示されたことで認識を変えたのですが、それは逆の方向だったのです。「大量破壊兵器はなかった」という記事を読んだ保守派は、ブッシュのイラク戦争への支持を大きく高めたのです。
なぜこんなことになるのか。ひとつの説明は、「リベラルは賢く、保守派はバカだ」でしょう。
そこで研究者は、リベラルが誤解している記事(幹細胞研究の禁止)を使って同じ実験をしてみました。するとこんどは、保守派がファクトチェックによって正しい方向に認識を変えたのに対し、リベラルはファクトにほとんど反応しなかったのです。
このことは、「ひとは見たいものしか見ない」だけでなく、「見たくないものを突きつけられると、自分の誤った信念にさらにしがみつく」ことを示しています。ファクトチェックに効果があるのは、自分にとって都合のいい「ファクト」だけなのです。
もちろんこれは、「ファクトチェックなどやめてしまえ」ということではありません。多数を占める政治的に中立(穏健)なひとたちは、ファクトによって正しい認識をもつことが期待できます。しかしその一方で、「ファクト」には社会の分断をさらに拡大する「不都合な効果」があるようです。
参考:Brendan Nyhan and Jason Reifler (2010) When Corrections Fail: The persistence of political misperceptions, Political Behavior
『週刊プレイボーイ』2021年6月7日発売号 禁・無断転載