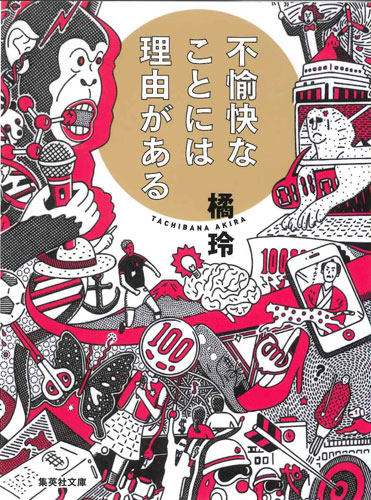「強く願えば夢はかなう」というポジティブシンキングは日本でも人気です。その源流であるポジティブ心理学では、うつ病や神経症など、こころのネガティブな側面だけを研究してきた従来の心理学を批判し、楽観主義で幸福に生きることを説きます。
水の入ったコップを見て「半分しかない」と思うか、「半分も残っている」と思うかは主観の問題ですが、心理的な効果は大きく異なります。生き物の進化の歴史を考えるならば、私たちがつねに悲観的(ネガティブ)にものごとを見るように「設計」されていることは明らかです。肉食獣がうようよいるサバンナで、天気がいいからとのんびり日光浴を楽しむような原始人はまっさきに死に絶えてしまったでしょう。
とはいえ石器時代より格段に安全になった現代社会で、おなじようにびくびくしながら生きる必要はありません。こころのネガティブな本性を考えれば、楽観的すぎるくらいの方がちょうどいいのです。
ここまでは説得力ある理屈ですが、これを子育てにあてはめ、「子どもはほめて伸ばす(自尊心を高める)」となると話が変わります。さまざまな研究によって、子どもをただほめるのは意味がないばかりか有害でもあるとわかってきたからです。
成績のかんばしくない大学生を無作為に選び、試験前に自信を持たせる応援メッセージ(君ならできる!)を毎週送ったところ、さらに成績が下がって落第必至になってしまいました。自尊心の低さと薬物依存や10代の妊娠などの問題行動のあいだに相関関係があることは間違いありませんが、ここから「自尊心が高いのはいいことだ」という結論は導けません。高い自尊心は、自尊心が低いのと同様に問題なのです。
研究者は、自尊心の高さの利点として実証されていることは2つしかないといいます。ひとつは自主性が高まることで、もうひとつは機嫌よく過ごせること。これにはよいと悪い面があって、信念に基づいて行動し、リスクを引き受ける強い意志を持ち、困難を克服したり失敗から立ち直るのには有効ですが、その反面、周囲の反対を無視して破滅的な行動に走ったり、自分が他人より優れていると思い込んだりします。ほめられた子どもは、それだけで満足して努力しようと思わないのです。
プロスポーツの世界では、アスリートに成功したプレイの映像を見せてポジティブなイメージを高めるのではなく、ミスをした場面を繰り返し見せるメンタルトレーニングが行なわれています。これは失敗を反省させるためではなく、試合でミスをしても過剰に反応しないようにする訓練です。どんな選手でもミスはします。勝敗を分けるのはそのときパニックを起こさず、不利な状況に冷静に対処できるかどうかなのです。
とはいえ、ポジティブシンキングがまったくのムダというわけではありません。
ドイツの小学校で英語を習いはじめた子どもたちに、「英語が話せたらどんないいことがあるか」作文を書かせたところ、夢を語ることで成績が大きく伸びることがわかりました。しかしこれには条件がひとつあります。
もっとも効果があったのは、英語の勉強がどれほど大変か、ネガティブなこともいっしょに考えた子どもたちだったのです。
参考:ロイ・バウマイスター、ジョン・ティアニー『WILLPOWER 意志力の科学』 インターシフト
『週刊プレイボーイ』2016年6月20日発売号
禁・無断転載